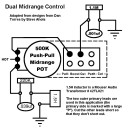撹乱的アグロデッキとは、ミッドレンジデッキやランプデッキのパワフルな脅威を展開されても、ゲームが終了するまでそれらの脅威から身を守り続け、アグロデッキの除去やディスカード、コントロールデッキのカウンターやコンボデッキの一撃必殺のプレッシャーからたちまち回復し、相手のゲームプランの根底を覆す様なデッキを指します。
通常「撹乱的アグロ」と言うと、ビートダウンとコントロールの中間的なデッキを指している事が多いです。少ない数の脅威が含まれているという点でミッドレンジのビートダウンデッキと異なっており、それら脅威の選定理由として「除去するのが難しい」と言う事に焦点を当てています。
まず、脅威をある程度展開し、それに対する除去を打ち消しなどで回避しつつ、対戦相手の戦略から逃げ切るためにバウンスや手札破壊、土地破壊のような「妨害呪文」で相手の戦略をギリギリの所で掻い潜りながら、毎ターン数点のダメージを刻み続ける事を基本戦略としています。
撹乱的アグロは、少数かつ特定の遅い脅威(フィニッシャー)に焦点を当てて妨害が可能です。その脅威を対象として事前に、または後からでも対処をして機能不全に陥らせて退ける事が可能な事からコンボデッキとランプデッキには強く出る事が出来ます。その一方、打ち消し呪文等の妨害呪文にデッキスロットを割く分、必然的にクリーチャーの線が細くなりやすく、また、戦場のアドバンテージ(ボードアドバンテージ)は他のデッキに比べて密度が低いので、クリーチャー同士の直接対決となりやすいビートダウン相手には不利になることが多いです。その中でもカウンターで防御する間もなく攻めてくる事で、コチラが相手の戦略を撹乱する隙が無い程のスピードを持っているウィニーを苦手としています。また、それぞれのカードの役割が明確になっている場合が多いので、理想的な回りをすれば強いですが、噛み合わないと簡単に崩れてしまうという脆さも併せ持っています。
しかしながらビートダウンとコントロールの中間だけに極端に苦手とするデッキは少ないです。汎用性は高いのですが、逆に言えば器用貧乏にもなりやすく、どの程度活躍できるかはプレイングと明確な戦略に左右されることが多いです。
通常はミッドレンジデッキよりも遅く、金魚が泳ぐスピードと同じ位の早さですが、マナコストの軽いクリーチャーを使う事により打ち消し呪文を回避しやすくしたり、逆にコチラの打ち消し呪文によって全体除去等の「戦場を攻撃する脅威」を受けにくくする事も可能です。
撹乱的アグロで重要なことは、ダメージソースがあり、かつその状態を長引かせることにあります。コチラがダメージディーラーを展開しているのであれば、普段はただ単に受け身な呪文でしか無い打ち消し呪文が、さながら《時間のねじれ/Time Warp》の様な働きをするのです。
例えば、100メートル走を真っ先に駆け抜けるのがアグロデッキだとしたら、コントロールデッキはできる限りゴールを遠くしようとする形ですが、撹乱的アグロはというと、相手より少しだけ早くゴールするという点に注目したデッキタイプであると言えるでしょう。相手を遅らせる事と自分が進むこと、その両方の効率のいい部分を取っていくのがこのアーキタイプの特徴です。
撹乱的アグロデッキ構築の為のヒント
◆撹乱的アグロデッキは、他のデッキのコンセプトを食い物にし、特定の脅威を奪い去り、機能障害に陥れます。古典的な打ち消し呪文は勿論の事、手札破壊や土地破壊、それに個別除去や時には全体除去も採用されています。《強迫/Duress》や《マナ漏出/Mana Leak》、《破滅的な行為/Pernicious Deed》などがこのデッキに採用されます。
◆全てのコストは効率よく!回答の為に脅威をプレイしてはいけません。あなたのクリーチャーは、フィールド内の痛みになるか、少なくともあなたに与える十分な利点があるべきなのです。撹乱的アグロはビートダウン戦略のデッキよりも「アグロ」なクリーチャーは少ないですが、戦場に出た時に「何か」をするクリーチャーが多いのが特徴です。それらは《永遠の証人/Eternal Witness》、《マラキールの門番/Gatekeeper of Malakir》、《ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph》、《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique》などのカード達です。
◆撹乱的アグロデッキは通常、自分自身を守るための方法を幾つか採用しています。しかし、自分のクリーチャーのほとんどは他のデッキのために不利益を与えることを試みる、妨害的要素が強いカードで構成されています。ここでは多くの場合、あなたがコントロールデッキに採用するものとは違って専用のボードコントロール要素を役割として与えられている事がほとんどで、コントロールデッキに搭載されるカードよりも、もっとコントロール要素が積極的なカード達が選ばれます。《ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator》、《吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk》、《ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine》、それと《業火のタイタン/Inferno Titan》の様なカード達が良きパートナーとなってくれるでしょう。
◆打ち消し呪文の枠には根本的な解決にはならないものの、時間稼ぎという点では万能の《遅延/Delay》が使われます。また、《神秘の蛇/Mystic Snake》や《造物の学者、ヴェンセール/Venser, Shaper Savant》といったカードは、クリーチャーでありながら対戦相手の呪文に干渉できるために、戦場の密度を高めつつ相手を遅らせることが可能な優秀なカードです。
◆近年では使われているクリーチャーが《密林の猿人/Kird Ape》や《喧騒の貧霊/Rumbling Slum》など、非常に打撃力のある強力なものになって来ています。ダメージディーラーが強力であればあるほど、《差し戻し/Remand》や《石の雨/Stone Rain》による「相手の行動の遅延」も相対的に強力になってくるのです。
通常「撹乱的アグロ」と言うと、ビートダウンとコントロールの中間的なデッキを指している事が多いです。少ない数の脅威が含まれているという点でミッドレンジのビートダウンデッキと異なっており、それら脅威の選定理由として「除去するのが難しい」と言う事に焦点を当てています。
まず、脅威をある程度展開し、それに対する除去を打ち消しなどで回避しつつ、対戦相手の戦略から逃げ切るためにバウンスや手札破壊、土地破壊のような「妨害呪文」で相手の戦略をギリギリの所で掻い潜りながら、毎ターン数点のダメージを刻み続ける事を基本戦略としています。
撹乱的アグロは、少数かつ特定の遅い脅威(フィニッシャー)に焦点を当てて妨害が可能です。その脅威を対象として事前に、または後からでも対処をして機能不全に陥らせて退ける事が可能な事からコンボデッキとランプデッキには強く出る事が出来ます。その一方、打ち消し呪文等の妨害呪文にデッキスロットを割く分、必然的にクリーチャーの線が細くなりやすく、また、戦場のアドバンテージ(ボードアドバンテージ)は他のデッキに比べて密度が低いので、クリーチャー同士の直接対決となりやすいビートダウン相手には不利になることが多いです。その中でもカウンターで防御する間もなく攻めてくる事で、コチラが相手の戦略を撹乱する隙が無い程のスピードを持っているウィニーを苦手としています。また、それぞれのカードの役割が明確になっている場合が多いので、理想的な回りをすれば強いですが、噛み合わないと簡単に崩れてしまうという脆さも併せ持っています。
しかしながらビートダウンとコントロールの中間だけに極端に苦手とするデッキは少ないです。汎用性は高いのですが、逆に言えば器用貧乏にもなりやすく、どの程度活躍できるかはプレイングと明確な戦略に左右されることが多いです。
通常はミッドレンジデッキよりも遅く、金魚が泳ぐスピードと同じ位の早さですが、マナコストの軽いクリーチャーを使う事により打ち消し呪文を回避しやすくしたり、逆にコチラの打ち消し呪文によって全体除去等の「戦場を攻撃する脅威」を受けにくくする事も可能です。
撹乱的アグロで重要なことは、ダメージソースがあり、かつその状態を長引かせることにあります。コチラがダメージディーラーを展開しているのであれば、普段はただ単に受け身な呪文でしか無い打ち消し呪文が、さながら《時間のねじれ/Time Warp》の様な働きをするのです。
例えば、100メートル走を真っ先に駆け抜けるのがアグロデッキだとしたら、コントロールデッキはできる限りゴールを遠くしようとする形ですが、撹乱的アグロはというと、相手より少しだけ早くゴールするという点に注目したデッキタイプであると言えるでしょう。相手を遅らせる事と自分が進むこと、その両方の効率のいい部分を取っていくのがこのアーキタイプの特徴です。
撹乱的アグロデッキ構築の為のヒント
◆撹乱的アグロデッキは、他のデッキのコンセプトを食い物にし、特定の脅威を奪い去り、機能障害に陥れます。古典的な打ち消し呪文は勿論の事、手札破壊や土地破壊、それに個別除去や時には全体除去も採用されています。《強迫/Duress》や《マナ漏出/Mana Leak》、《破滅的な行為/Pernicious Deed》などがこのデッキに採用されます。
◆全てのコストは効率よく!回答の為に脅威をプレイしてはいけません。あなたのクリーチャーは、フィールド内の痛みになるか、少なくともあなたに与える十分な利点があるべきなのです。撹乱的アグロはビートダウン戦略のデッキよりも「アグロ」なクリーチャーは少ないですが、戦場に出た時に「何か」をするクリーチャーが多いのが特徴です。それらは《永遠の証人/Eternal Witness》、《マラキールの門番/Gatekeeper of Malakir》、《ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph》、《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique》などのカード達です。
◆撹乱的アグロデッキは通常、自分自身を守るための方法を幾つか採用しています。しかし、自分のクリーチャーのほとんどは他のデッキのために不利益を与えることを試みる、妨害的要素が強いカードで構成されています。ここでは多くの場合、あなたがコントロールデッキに採用するものとは違って専用のボードコントロール要素を役割として与えられている事がほとんどで、コントロールデッキに搭載されるカードよりも、もっとコントロール要素が積極的なカード達が選ばれます。《ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator》、《吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk》、《ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine》、それと《業火のタイタン/Inferno Titan》の様なカード達が良きパートナーとなってくれるでしょう。
◆打ち消し呪文の枠には根本的な解決にはならないものの、時間稼ぎという点では万能の《遅延/Delay》が使われます。また、《神秘の蛇/Mystic Snake》や《造物の学者、ヴェンセール/Venser, Shaper Savant》といったカードは、クリーチャーでありながら対戦相手の呪文に干渉できるために、戦場の密度を高めつつ相手を遅らせることが可能な優秀なカードです。
◆近年では使われているクリーチャーが《密林の猿人/Kird Ape》や《喧騒の貧霊/Rumbling Slum》など、非常に打撃力のある強力なものになって来ています。ダメージディーラーが強力であればあるほど、《差し戻し/Remand》や《石の雨/Stone Rain》による「相手の行動の遅延」も相対的に強力になってくるのです。
コントロールとは、多かれ少なかれ差はありますが、聞いたままの意味です。これらのデッキは、リソースのアドバンテージを蓄積しようと試み、脅威を含む動きを取らせない様にと対戦相手を選択権の外へと追い込む事を目指します。
通常(しかし常時ではありませんが)、ミッドレンジやランプデッキに搭載されているものと同等の脅威でゲームを終焉へと導きます。ミッドレンジやランプデッキは出来る限りスグにそれらの脅威(フィニッシャー)を唱える事に焦点を当てていますが、このデッキはそこに焦点を当ててはいません。その代わりに、このデッキのフィニッシャーは「既に安全が確保されたゲームを終わらせる為」に使用されるのです。あるいは、フィニッシャー自体のサイズや相手の脅威を除去する能力のおかげで、自分自身が盤面を固定させるツールとして機能しているのが特徴です。
時にマジックと言う名のレースは、それぞれが思い描いた計画を、相手より先に実行することがポイントとなっています。それを実行するまでの間に、私達は脅威とそれに対する回答を等価交換している事が多いのです。
例えば相手の《灰色熊/Grizzly Bears》に《ショック/Shock》を撃ち、自分の《呆然/Stupor》に《マナ漏出/Mana Leak》を撃たれ、相手の《分解/Disintegrate》を《治癒の軟膏/Healing Salve》で回避するといったように。その結果、(時には脅威が少し残ったり、脅威に対する明確な回答が捻出できなかったりする場合もありますが)デッキに入ってる脅威の大半が消耗され、レースの後半戦においてはスムーズに物事が進むようになるのです。
また、アーキタイプと言う枠組みの中以外でも「コントロール」という言葉が使われる場合があります。それは主に対戦相手のデッキと場の状況に合わせたプレイングスタイルを指す場合に使われる事が多い言葉です。そうする事により、デッキの優劣が変わるのです。
例えば自分がレベルデッキを使用しているとして、相手の白青コントロールと対峙した場合は、ライブラリーからリクルート能力で次々とレベル達を呼び出して攻撃し続ければ、対戦相手はレベル達を残らず除去するのは難しくなるので、余剰のカードをドローする事も出来ずに20点のダメージを叩き込まれる事になるでしょう。それに対しZooスタイルのデッキと戦う場合は、呪文をプレイするタイミングを遅くし、最低限クリーチャー同士の相打ち等の1対1交換やアドバンテージやリソースの消費を最小限に抑えつつ、なるべく試合を長引かせて相手が息切れする様な戦略を取り、頑丈で豊富なレベル達の強固な守りで試合を切り抜ける事を目指すべきなのです。
このような考え方は広く知られており、しばしば「ハード/ソフト」や「アグロ/コントロール」と呼ばれています。「アグロ」サイドでは自らを省みずに能動的に攻め、「コントロール」サイドでは試合の流れに乗り、受動的に攻める事を指しています。
コントロールデッキ最大の魅力であり、他のアーキタイプにはない特徴とはズバリ「相手のカードを切り捨てられる」ということなのです。主な例を4つ挙げます。
◆低コストで相手の脅威を消去する事。つまり、《神の怒り/Wrath of God》や《地震/Earthquake》のような1つの呪文で多数のクリーチャーを除去する事(カードアドバンテージとボードアドバンテージ)、《怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath》のような重い呪文を停止させるには《取り消し/Cancel》の様な比較的安価な呪文を使用する事(テンポアドバンテージ)、《殺戮/Slay》を唱えて緑の大型クリーチャーを殺しつつカードを引く事(テンポアドバンテージとカードアドバンテージとボードアドバンテージ)、1枚の《呆然/Stupor》で相手の手札を2枚ノックアウトさせる事(カードアドバンテージ。手札破壊には相手の手札を見てから捨てさせるものもあるので、もしも相手の手札が見られたなら、それは相手の行動がある程度先読みする事が出来る様になる事を意味しているので、それも内包的なアドバンテージに繋がる)などということが挙げられます。相手には「ずるい」と思われるかもしれませんが、それらはフィニッシャーを着地させる時間と機会を作りだす為に重要なことです。
◆相手の脅威に対しての回答として、コチラの脅威をプレイしてはいけません。コントロールデッキは軽いクリーチャー呪文などを唱えないので、相手の率先した呪文(ボクシングで言うならジャブ)に対処的な呪文をぶつけていくことが出来ます。また、時には対処的な呪文の対象が見つからないかもしれませんが、それは見えないカードアドバンテージを獲得していると言っても差し支えありません。なぜならば、コントロールデッキは試合が長引けば長引くほど強くなる性質を持っている為、相手が率先して呪文を唱えないという事は必然的に試合時間が伸びるという事に他ならないからです。
◆シナジーを破壊する事。全ての呪文に対して直接手を下さなかったとしても、「良い形」になっているものの内、どれか一つを除外する事により、機能不全に陥らせる事が出来ます。もしもデッキ内にこのギミックが入っていないなら注意する必要は無いかもしれませんが、この最も極端な例は、クリーチャーにオーラをエンチャントする事です。
◆自分の準備が整うまで試合を長引かせる事。《サバンナ・ライオン/Savannah Lions》はゲームの初期ターンでは有効な呪文ですが、10ターン目、土地が必要枚数以上出ている時に引いて来たそれは、失望以外の何物でもありません。
全てのマナを利用して上記の項目を滞りなく行えた場合、対戦相手のライブラリーの中身は極めて少ない脅威しか残されていないハズです。なぜならば対戦相手は幾度ものドローフェイズによって有効札を引き終えており、ライブラリーの密度が薄くなっている為、多くのデッキは期待はずれの可能性が高いドローに満たされるからです。この状態こそが、対戦相手をコントロールしている状態、すなわち倒す準備が整ったということに他なりません。ビートダウンデッキと戦う際にこのような事を行うには難しく思えるかもしれませんが、メタゲームやマッチアップ、カードプールをよく考えてからデッキ構築を行えば勝つ事は可能なのです。
このアーキタイプはどんなフォーマットでも出会う可能性がありますが、これを読んでいる人の中には速度が遅く、魅力的なコンボも搭載していないコントロールデッキに無関心な人もいるかもしれません。もしそうなら、相手がコントロールデッキをどのように構築し、どのような理念に基づいて動かしているかを教えましょう。コントロールデッキの概念として、有益なサンプルになることを願っています。
まずは指標についてです。最も一般的な指標のひとつとして、《神の怒り/Wrath of God》の効果を最大限に発揮させるために、自分のデッキに《神の怒り/Wrath of God》と同枚数程度のクリーチャーしか積んでいない様なデッキがありますが、これは相手がクリーチャーに頼らないデッキを使っていた場合や、カウンター呪文、ディスカード呪文を使われた場合には有効に働かない指標となりえてしまいます。なので、デッキには対戦相手の脅威に対する明確な回答を積んでいなければならないのです。もしも対戦相手がパーマネントを毎ターン1枚ずつしかプレイして来ない様な相手ならば、あなたが危険にさらされる前に、対戦相手は脅威を使い尽くしてしまうでしょう。しかし、あなたの土地が4枚立っている時には単純に呪文をプレイしない様な相手や、土地を置いてターンを終了するだけなら、あなたは積極的に動いてはいけません。それがたとえ手札が7枚を超えてディスカードをすることになっても、です。
もしも土地を多く引きすぎた場合には、あまり多く動かずに長期消耗戦に持ち込むべきです。その際、対戦相手がコントロールデッキだった場合に気をつけなければならない呪文はドロー呪文、インスタント速度の脅威、フラッシュバック等の墓地から唱えられる呪文、それと、あなたのフィニッシャーや有効手段に対してのカウンター呪文等の脅威です。
このメッセージはあなたの考え方を発展させる事によって、狡猾な対戦相手ですらもまだ気がついていない有効な打開策をあなたが先に閃き、アドバンテージをとらせる為のモノです。つまり解決策とは、あなたのデッキエンジンであり、指標なのです。デッキ構築の時点から戦いは始まっているのですから。
通常(しかし常時ではありませんが)、ミッドレンジやランプデッキに搭載されているものと同等の脅威でゲームを終焉へと導きます。ミッドレンジやランプデッキは出来る限りスグにそれらの脅威(フィニッシャー)を唱える事に焦点を当てていますが、このデッキはそこに焦点を当ててはいません。その代わりに、このデッキのフィニッシャーは「既に安全が確保されたゲームを終わらせる為」に使用されるのです。あるいは、フィニッシャー自体のサイズや相手の脅威を除去する能力のおかげで、自分自身が盤面を固定させるツールとして機能しているのが特徴です。
時にマジックと言う名のレースは、それぞれが思い描いた計画を、相手より先に実行することがポイントとなっています。それを実行するまでの間に、私達は脅威とそれに対する回答を等価交換している事が多いのです。
例えば相手の《灰色熊/Grizzly Bears》に《ショック/Shock》を撃ち、自分の《呆然/Stupor》に《マナ漏出/Mana Leak》を撃たれ、相手の《分解/Disintegrate》を《治癒の軟膏/Healing Salve》で回避するといったように。その結果、(時には脅威が少し残ったり、脅威に対する明確な回答が捻出できなかったりする場合もありますが)デッキに入ってる脅威の大半が消耗され、レースの後半戦においてはスムーズに物事が進むようになるのです。
また、アーキタイプと言う枠組みの中以外でも「コントロール」という言葉が使われる場合があります。それは主に対戦相手のデッキと場の状況に合わせたプレイングスタイルを指す場合に使われる事が多い言葉です。そうする事により、デッキの優劣が変わるのです。
例えば自分がレベルデッキを使用しているとして、相手の白青コントロールと対峙した場合は、ライブラリーからリクルート能力で次々とレベル達を呼び出して攻撃し続ければ、対戦相手はレベル達を残らず除去するのは難しくなるので、余剰のカードをドローする事も出来ずに20点のダメージを叩き込まれる事になるでしょう。それに対しZooスタイルのデッキと戦う場合は、呪文をプレイするタイミングを遅くし、最低限クリーチャー同士の相打ち等の1対1交換やアドバンテージやリソースの消費を最小限に抑えつつ、なるべく試合を長引かせて相手が息切れする様な戦略を取り、頑丈で豊富なレベル達の強固な守りで試合を切り抜ける事を目指すべきなのです。
このような考え方は広く知られており、しばしば「ハード/ソフト」や「アグロ/コントロール」と呼ばれています。「アグロ」サイドでは自らを省みずに能動的に攻め、「コントロール」サイドでは試合の流れに乗り、受動的に攻める事を指しています。
コントロールデッキ最大の魅力であり、他のアーキタイプにはない特徴とはズバリ「相手のカードを切り捨てられる」ということなのです。主な例を4つ挙げます。
◆低コストで相手の脅威を消去する事。つまり、《神の怒り/Wrath of God》や《地震/Earthquake》のような1つの呪文で多数のクリーチャーを除去する事(カードアドバンテージとボードアドバンテージ)、《怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath》のような重い呪文を停止させるには《取り消し/Cancel》の様な比較的安価な呪文を使用する事(テンポアドバンテージ)、《殺戮/Slay》を唱えて緑の大型クリーチャーを殺しつつカードを引く事(テンポアドバンテージとカードアドバンテージとボードアドバンテージ)、1枚の《呆然/Stupor》で相手の手札を2枚ノックアウトさせる事(カードアドバンテージ。手札破壊には相手の手札を見てから捨てさせるものもあるので、もしも相手の手札が見られたなら、それは相手の行動がある程度先読みする事が出来る様になる事を意味しているので、それも内包的なアドバンテージに繋がる)などということが挙げられます。相手には「ずるい」と思われるかもしれませんが、それらはフィニッシャーを着地させる時間と機会を作りだす為に重要なことです。
◆相手の脅威に対しての回答として、コチラの脅威をプレイしてはいけません。コントロールデッキは軽いクリーチャー呪文などを唱えないので、相手の率先した呪文(ボクシングで言うならジャブ)に対処的な呪文をぶつけていくことが出来ます。また、時には対処的な呪文の対象が見つからないかもしれませんが、それは見えないカードアドバンテージを獲得していると言っても差し支えありません。なぜならば、コントロールデッキは試合が長引けば長引くほど強くなる性質を持っている為、相手が率先して呪文を唱えないという事は必然的に試合時間が伸びるという事に他ならないからです。
◆シナジーを破壊する事。全ての呪文に対して直接手を下さなかったとしても、「良い形」になっているものの内、どれか一つを除外する事により、機能不全に陥らせる事が出来ます。もしもデッキ内にこのギミックが入っていないなら注意する必要は無いかもしれませんが、この最も極端な例は、クリーチャーにオーラをエンチャントする事です。
◆自分の準備が整うまで試合を長引かせる事。《サバンナ・ライオン/Savannah Lions》はゲームの初期ターンでは有効な呪文ですが、10ターン目、土地が必要枚数以上出ている時に引いて来たそれは、失望以外の何物でもありません。
全てのマナを利用して上記の項目を滞りなく行えた場合、対戦相手のライブラリーの中身は極めて少ない脅威しか残されていないハズです。なぜならば対戦相手は幾度ものドローフェイズによって有効札を引き終えており、ライブラリーの密度が薄くなっている為、多くのデッキは期待はずれの可能性が高いドローに満たされるからです。この状態こそが、対戦相手をコントロールしている状態、すなわち倒す準備が整ったということに他なりません。ビートダウンデッキと戦う際にこのような事を行うには難しく思えるかもしれませんが、メタゲームやマッチアップ、カードプールをよく考えてからデッキ構築を行えば勝つ事は可能なのです。
このアーキタイプはどんなフォーマットでも出会う可能性がありますが、これを読んでいる人の中には速度が遅く、魅力的なコンボも搭載していないコントロールデッキに無関心な人もいるかもしれません。もしそうなら、相手がコントロールデッキをどのように構築し、どのような理念に基づいて動かしているかを教えましょう。コントロールデッキの概念として、有益なサンプルになることを願っています。
まずは指標についてです。最も一般的な指標のひとつとして、《神の怒り/Wrath of God》の効果を最大限に発揮させるために、自分のデッキに《神の怒り/Wrath of God》と同枚数程度のクリーチャーしか積んでいない様なデッキがありますが、これは相手がクリーチャーに頼らないデッキを使っていた場合や、カウンター呪文、ディスカード呪文を使われた場合には有効に働かない指標となりえてしまいます。なので、デッキには対戦相手の脅威に対する明確な回答を積んでいなければならないのです。もしも対戦相手がパーマネントを毎ターン1枚ずつしかプレイして来ない様な相手ならば、あなたが危険にさらされる前に、対戦相手は脅威を使い尽くしてしまうでしょう。しかし、あなたの土地が4枚立っている時には単純に呪文をプレイしない様な相手や、土地を置いてターンを終了するだけなら、あなたは積極的に動いてはいけません。それがたとえ手札が7枚を超えてディスカードをすることになっても、です。
もしも土地を多く引きすぎた場合には、あまり多く動かずに長期消耗戦に持ち込むべきです。その際、対戦相手がコントロールデッキだった場合に気をつけなければならない呪文はドロー呪文、インスタント速度の脅威、フラッシュバック等の墓地から唱えられる呪文、それと、あなたのフィニッシャーや有効手段に対してのカウンター呪文等の脅威です。
このメッセージはあなたの考え方を発展させる事によって、狡猾な対戦相手ですらもまだ気がついていない有効な打開策をあなたが先に閃き、アドバンテージをとらせる為のモノです。つまり解決策とは、あなたのデッキエンジンであり、指標なのです。デッキ構築の時点から戦いは始まっているのですから。
コンボデッキとは、デッキ全体を集束させ、数枚のカードの組み合わせによって出来る限り迅速にゲームを終了させるデッキの事を指します。
「コンボ」とは「コンビネーション」の略称で、最広義では2つ以上のあらゆるオブジェクトの連係の事を指す言葉ですが、MTGに於いては勝利に直結する2つ以上の効果の組み合わせのことを指すことが多いです。(勝利に直結しないコンボはギミックと呼ばれており、動作自体でなくその「相乗効果を持つ特性」の事はシナジーと呼ばれています。)
このアーキタイプは他のアーキタイプと違い、非常に特殊なプレイングやデッキ構築を要します。他のアーキタイプと特に大きく違う点は、基本的にはコンボの真価を発揮出来るチャンスが来るまでは待ち続ける、といった点です。とは言ってもただ待っているのだけではなく、ライブラリー操作やサーチ、その他の呪文を駆使しながら、場や手札を整えて、その時を虎視眈々と待ち続けます。そして、全てが整ったのならば然るべくして爆発的にマナを増やしたり、無限連鎖を行なったりして勝利を掴み取るのです。
このアーキタイプは深刻な弱点を持ちながらも己の戦略を着実に遂行しようと試みる「一発逆転」的なデッキとして扱われる事が多いです。つまりコンボデッキとは、コンボが完成するまでの間はハンデを背負っており、本質的には逆転を目指しているデッキ、という事になります。やるかやられるか、まさにこの言葉がピタリと当て嵌まるでしょう。
コンボデッキは大量のアドバンテージを得ることができるか、それ自体が勝利に直結するような強力なコンボを搭載しています。それらの種類にはいくつかありますが、例えば、20点以上のダメージを一気に与える、ライブラリーのカードを60枚引き切らせる、無限のライフを得る、対戦相手が何もできない状況を維持する、永遠に相手へターンを渡さない、勝利条件を即座に満たす、等です。
コンボ自体は非常に強力で、あなたを即座に勝利に導いてくれる事でしょう。しかしながら、それはあくまでコンボが完成したらの話であって、完成できないコンボは所詮「机上の空論」でしかないのです。
デッキを60枚以下にする事は出来ませんが、コンボに使用するカードはほんの数枚だけです。これはルールなので覆すことは出来ません。しかもコンボパーツが手札に来たとしても、それをプレイ出来なければ意味をなさない場合がほとんどです。
これらコンボデッキに共通している事は、「そのコンボの為にデッキ事態が収束するように設計されている」、といった事です。
その条件を全て満たし、一瞬でもその「収束点」に到達できたのだとすれば、今まで抱えていた不安は全て吹き飛び、あなたに勝利という名の天使が舞い降りて来る事でしょう。
コンボをデッキに実装するには主に2つの方法があります。1つはコンボパーツが揃うまで生き残り、「コンボを妨害するカード」に対処する為のカードを引き寄せる事が容易になる様な、「コンボ専用」のコンボデッキを構築する事、もう1つは先の方法と「生き残る」といった所で重なる部分もありますが、勝利条件として既存のデッキにコンボを追加するといった方法です。
どちらの方法にせよ、コンボデッキにとって重要なのは、平均して何ターンでそのコンボが完成するか、という事です。アグロデッキはおおよそ5ターン程度で決着を付けにかかって来るので、勝率を気にするのであれば、それくらいを目安として考えなくてはいけません。
そして、これも重要なことですが、相手はただの「金魚」ではなく対戦相手だということです。あなたはコンボが完成するまでの間はほとんど何の抵抗もせずに打たれ続けるでしょうが、相手はそうではありません。様々な方法であなたのコンボを防いでくるでしょう。クロックの速さはもちろんの事、手札破壊、カウンター呪文、マナ基盤の破壊等です。特に《強迫/Duress》や《オアリムの詠唱/Orim’s Chant》には気をつけましょう。
コンボとは、多角的に熟慮した上で思いつくかもしれないし、天啓であるかのように突然閃くこともあります。ただ一つ言える事は、プロツアーやグランプリを征服したコンボデッキは誰もがそれを知っています。つまり、対策が取られやすいという事に他なりません。
対策を取られない様にする為にもオリジナルコンボの採用をオススメしますが、ハッキリ言って、オリジナルのコンボを見つけるのは非常に難しい事です。しかし、MTGには数限りないカードがあるので、まだ発見されていないコンボが埋れているハズです。例えるならばそれは、今はもう忘れ去られてしまった鉱山から金を見つける事と同じ事だと言えるでしょう。日頃から洞察力を鍛えていれば、もしかしたら突然、フラッシュの様に未知なるコンボを閃き、あなたが最初の発見者になる事が出来るかもしれません。
ただし、たとえ生み出される効果が強力であっても、必要なパーツが多過ぎたり重過ぎたりする場合、そのコンボが完成するまでに対抗手段を用意されたり敗北したりしてしまうため、実質的に強力とは言えません。また、コンボに特化する事によって成功率と速度は高まりますが、そのようなデッキは往々にして偏った構成になっているので、一度失敗すると何もできずに敗北してしまう事が多いです。もしコンボが失敗したしても、コンボパーツ自体が単体である程度戦えるような、安定感のあるデッキは強力と言われています。しかし、コンボの成功率が高すぎて失敗しないデッキは、それ以上の脅威となるでしょう。
コンボデッキ構築の為のヒント
「コンボ」とは「コンビネーション」の略称で、最広義では2つ以上のあらゆるオブジェクトの連係の事を指す言葉ですが、MTGに於いては勝利に直結する2つ以上の効果の組み合わせのことを指すことが多いです。(勝利に直結しないコンボはギミックと呼ばれており、動作自体でなくその「相乗効果を持つ特性」の事はシナジーと呼ばれています。)
このアーキタイプは他のアーキタイプと違い、非常に特殊なプレイングやデッキ構築を要します。他のアーキタイプと特に大きく違う点は、基本的にはコンボの真価を発揮出来るチャンスが来るまでは待ち続ける、といった点です。とは言ってもただ待っているのだけではなく、ライブラリー操作やサーチ、その他の呪文を駆使しながら、場や手札を整えて、その時を虎視眈々と待ち続けます。そして、全てが整ったのならば然るべくして爆発的にマナを増やしたり、無限連鎖を行なったりして勝利を掴み取るのです。
このアーキタイプは深刻な弱点を持ちながらも己の戦略を着実に遂行しようと試みる「一発逆転」的なデッキとして扱われる事が多いです。つまりコンボデッキとは、コンボが完成するまでの間はハンデを背負っており、本質的には逆転を目指しているデッキ、という事になります。やるかやられるか、まさにこの言葉がピタリと当て嵌まるでしょう。
コンボデッキは大量のアドバンテージを得ることができるか、それ自体が勝利に直結するような強力なコンボを搭載しています。それらの種類にはいくつかありますが、例えば、20点以上のダメージを一気に与える、ライブラリーのカードを60枚引き切らせる、無限のライフを得る、対戦相手が何もできない状況を維持する、永遠に相手へターンを渡さない、勝利条件を即座に満たす、等です。
コンボ自体は非常に強力で、あなたを即座に勝利に導いてくれる事でしょう。しかしながら、それはあくまでコンボが完成したらの話であって、完成できないコンボは所詮「机上の空論」でしかないのです。
デッキを60枚以下にする事は出来ませんが、コンボに使用するカードはほんの数枚だけです。これはルールなので覆すことは出来ません。しかもコンボパーツが手札に来たとしても、それをプレイ出来なければ意味をなさない場合がほとんどです。
これらコンボデッキに共通している事は、「そのコンボの為にデッキ事態が収束するように設計されている」、といった事です。
その条件を全て満たし、一瞬でもその「収束点」に到達できたのだとすれば、今まで抱えていた不安は全て吹き飛び、あなたに勝利という名の天使が舞い降りて来る事でしょう。
コンボをデッキに実装するには主に2つの方法があります。1つはコンボパーツが揃うまで生き残り、「コンボを妨害するカード」に対処する為のカードを引き寄せる事が容易になる様な、「コンボ専用」のコンボデッキを構築する事、もう1つは先の方法と「生き残る」といった所で重なる部分もありますが、勝利条件として既存のデッキにコンボを追加するといった方法です。
どちらの方法にせよ、コンボデッキにとって重要なのは、平均して何ターンでそのコンボが完成するか、という事です。アグロデッキはおおよそ5ターン程度で決着を付けにかかって来るので、勝率を気にするのであれば、それくらいを目安として考えなくてはいけません。
そして、これも重要なことですが、相手はただの「金魚」ではなく対戦相手だということです。あなたはコンボが完成するまでの間はほとんど何の抵抗もせずに打たれ続けるでしょうが、相手はそうではありません。様々な方法であなたのコンボを防いでくるでしょう。クロックの速さはもちろんの事、手札破壊、カウンター呪文、マナ基盤の破壊等です。特に《強迫/Duress》や《オアリムの詠唱/Orim’s Chant》には気をつけましょう。
コンボとは、多角的に熟慮した上で思いつくかもしれないし、天啓であるかのように突然閃くこともあります。ただ一つ言える事は、プロツアーやグランプリを征服したコンボデッキは誰もがそれを知っています。つまり、対策が取られやすいという事に他なりません。
対策を取られない様にする為にもオリジナルコンボの採用をオススメしますが、ハッキリ言って、オリジナルのコンボを見つけるのは非常に難しい事です。しかし、MTGには数限りないカードがあるので、まだ発見されていないコンボが埋れているハズです。例えるならばそれは、今はもう忘れ去られてしまった鉱山から金を見つける事と同じ事だと言えるでしょう。日頃から洞察力を鍛えていれば、もしかしたら突然、フラッシュの様に未知なるコンボを閃き、あなたが最初の発見者になる事が出来るかもしれません。
ただし、たとえ生み出される効果が強力であっても、必要なパーツが多過ぎたり重過ぎたりする場合、そのコンボが完成するまでに対抗手段を用意されたり敗北したりしてしまうため、実質的に強力とは言えません。また、コンボに特化する事によって成功率と速度は高まりますが、そのようなデッキは往々にして偏った構成になっているので、一度失敗すると何もできずに敗北してしまう事が多いです。もしコンボが失敗したしても、コンボパーツ自体が単体である程度戦えるような、安定感のあるデッキは強力と言われています。しかし、コンボの成功率が高すぎて失敗しないデッキは、それ以上の脅威となるでしょう。
コンボデッキ構築の為のヒント
◆コンボデッキを構築するという事は、レーシングカーを組み立てていると置き換えて考えると理解がしやすい。まず、コンボデッキを構築する為のカードの組み合わせ、つまり「コンボ」を見つけなければならない。この過程はエンジンの組み立て作業に例えられる。何故ならばレーシングカーは、エンジンが無ければ動かないからだ。この例としては《修繕/Tinker》+《荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus》や《ぬいぐるみ人形/Stuffy Doll》+《罪の意識/Guilty Conscience》などがある。
◆エンジンに燃料が必要な様に、コンボを素早く決める為にも大量のマナが必要不可欠だ。《ドラゴンの嵐/Dragonstorm》のコンボを起動させるには、《睡蓮の花/Lotus Bloom》や《炎の儀式/Rite of Flame》の様な、燃料に該当するカードを大量に唱える必要がある。
◆もう一つのポイントは、レーシングカーの 「ボディ」のように、自分のコンボを相手から守る方法だ。ボディが貧弱だった場合、エンジン自体が落とされてしまう可能性が高いからだ。コンボを守るために役立つカードは、コントロールデッキや撹乱的アグロデッキで使用されている《万の眠り/Gigadrowse》、または《強迫/Duress》のようなカードだ。
◆車が走り出す為には、エンジンをオンにするキーが必要だ。ドローカードとチューターカードは、自分のデッキ内に「コンボパーツ」を探しにいけることが強みだ。《牧歌的な教示者/Idyllic Tutor》、《加工/Fabricate》、《思案/Ponder》は、その仕事をこなしてくれるだろう。
ランプデッキとは、土地やアーティファクト等の恒久的なマナ加速によって使用可能なマナ領域を押し上げ、重いフィニッシャーに繋げるアーキタイプの総称です。「ビッグ・マナ」や「ターボランド」といった場合もほぼ同じアーキタイプを指しています。
ランプデッキはボードへの脅威を展開していき、ボード・アドバンテージを積み重ねていくミッドレンジとは対照的で、自分が望むマナ域までマナ・アドバンテージを取り続け、使用できるマナ域の押し上げを図ります。
ほぼ共通して緑を中心とした構成になる事が多いですが、マナ加速の際に色マナを確保しやすく、無理なく多色化が可能なので、カラーパターンは様々です。緑単色のものから、複数の色からパワーカードをかき集めたグッドスタッフ系のデッキまで幅広いバリエーションがあります。
通常、緑のマナ加速手段にはマナ・クリーチャーを使用するのが一般的ですが、自分の全体除去との相性が悪い事もあり、投入を控えるケースは珍しくありません。その点でも、軽いマナ・クリーチャーを重視してテンポロスの大きい土地サーチ呪文やマナ・アーティファクトを嫌う緑系のミッドレンジとは対照的になっています。
また、近年ではアーティファクトでも土地サーチを出来るものが増えてきており、緑を全く使用せずともランプデッキを組めるようになってきています。
このアーキタイプは序盤の数ターンをマナ加速に費やし、より重く、より強力な呪文を対戦相手よりも早いターンに唱えようと試みます。なので、ランプデッキは他のアーキタイプと比べて、「プレイ可能だ」とみなされるマナ・コストのスペースを拡大することが必要不可欠です。なぜならば、土地サーチ呪文やマナ・アーティファクトなどの恒久的マナ加速によって他のデッキよりも素早く、そして確実に高マナ域に到達する事が可能で、大型クリーチャーや重い呪文を連打、物量で対戦相手を圧倒する事に焦点を当てているからです。
何故重い呪文を連打する事が強いのかと言うと、6マナのカードの優位性は2マナのカード3枚よりも、3マナのカード2枚のそれよりも優れている傾向にある、といった理由が挙げられるでしょう。
ランプデッキは大きな脅威、所謂「フィニッシャーとするカード」を採用する場合に於いては、マナコストを無視して考え、カード1枚における仕事量の多いモノを採用する傾向にあります。これはとても基本的な事で、《休耕地/Fallow Earth》と《すき込み/Plow Under》比べるとよく分かると思いますが、自分の望むマナ域まで確実にマナが出る状況、つまり唱えるために十分なマナが出る状態なのであれば、《すき込み/Plow Under》の方が優位性が高い、と言うことです。
このアーキタイプはマナ・アドバンテージを伸ばしていく事だけに注目されがちですが、クリーチャー除去や土地破壊で相手を減速させて相対的な速度を得ることも多いのが事実です。この点ではコントロールデッキとしての側面が強いですが、しかしながらその一方で、このアーキタイプの根幹である能動的な動きはむしろアグロデッキやコンボデッキのそれに近いものがあります。このような事から、所謂3大アーキタイプのどれかに内包される概念ではなく、独立したアーキタイプとして扱われているのです。
基本的にマナ・アドバンテージの呪文を妨害するよりも、クリーチャーを除去する方が比較的容易に行えます。その事からランプデッキはマナ・クリーチャーよりも土地やアーティファクト等の恒久的なマナ加速を用いる事を原則としています。つまりこれが何を意味しているのかというと、ランプデッキが正常にランプした場合とアグロデッキが正常にカーブした場合とでは、他のアーキタイプからの干渉を受け辛いランプデッキが有利になるのが一般的だ、という事に他なりません。
その一方で、このアーキタイプには明確な欠点が2つあります。まず1つに、ランプデッキはマナ加速に特化している為、ランプカードを引きすぎても引かなすぎてもフィニッシャーたる脅威を展開する事が出来ないので、安定性に欠けるといった事が挙げられます。マナ加速の為に手札を消費してしまうので、ハンド・アドバンテージの確保や、ランプの為のソーサリー呪文にマナを割いてしまうので、インスタント・タイミングで動きにくい事も安定性を欠く要因となっています。2つ目に、このデッキは1つ、または複数の大きな脅威に依存していて、それらを達成する為に複数回のマナ加速を行いますが、それは逆説的に、その最後に着地させる脅威をカウンターされる、もしくは取り除かれてしまった場合には「ガス欠」を起こしてしまう、といった事を意味しているのです。
ランプデッキ構築の為のヒント
ランプデッキはボードへの脅威を展開していき、ボード・アドバンテージを積み重ねていくミッドレンジとは対照的で、自分が望むマナ域までマナ・アドバンテージを取り続け、使用できるマナ域の押し上げを図ります。
ほぼ共通して緑を中心とした構成になる事が多いですが、マナ加速の際に色マナを確保しやすく、無理なく多色化が可能なので、カラーパターンは様々です。緑単色のものから、複数の色からパワーカードをかき集めたグッドスタッフ系のデッキまで幅広いバリエーションがあります。
通常、緑のマナ加速手段にはマナ・クリーチャーを使用するのが一般的ですが、自分の全体除去との相性が悪い事もあり、投入を控えるケースは珍しくありません。その点でも、軽いマナ・クリーチャーを重視してテンポロスの大きい土地サーチ呪文やマナ・アーティファクトを嫌う緑系のミッドレンジとは対照的になっています。
また、近年ではアーティファクトでも土地サーチを出来るものが増えてきており、緑を全く使用せずともランプデッキを組めるようになってきています。
このアーキタイプは序盤の数ターンをマナ加速に費やし、より重く、より強力な呪文を対戦相手よりも早いターンに唱えようと試みます。なので、ランプデッキは他のアーキタイプと比べて、「プレイ可能だ」とみなされるマナ・コストのスペースを拡大することが必要不可欠です。なぜならば、土地サーチ呪文やマナ・アーティファクトなどの恒久的マナ加速によって他のデッキよりも素早く、そして確実に高マナ域に到達する事が可能で、大型クリーチャーや重い呪文を連打、物量で対戦相手を圧倒する事に焦点を当てているからです。
何故重い呪文を連打する事が強いのかと言うと、6マナのカードの優位性は2マナのカード3枚よりも、3マナのカード2枚のそれよりも優れている傾向にある、といった理由が挙げられるでしょう。
ランプデッキは大きな脅威、所謂「フィニッシャーとするカード」を採用する場合に於いては、マナコストを無視して考え、カード1枚における仕事量の多いモノを採用する傾向にあります。これはとても基本的な事で、《休耕地/Fallow Earth》と《すき込み/Plow Under》比べるとよく分かると思いますが、自分の望むマナ域まで確実にマナが出る状況、つまり唱えるために十分なマナが出る状態なのであれば、《すき込み/Plow Under》の方が優位性が高い、と言うことです。
このアーキタイプはマナ・アドバンテージを伸ばしていく事だけに注目されがちですが、クリーチャー除去や土地破壊で相手を減速させて相対的な速度を得ることも多いのが事実です。この点ではコントロールデッキとしての側面が強いですが、しかしながらその一方で、このアーキタイプの根幹である能動的な動きはむしろアグロデッキやコンボデッキのそれに近いものがあります。このような事から、所謂3大アーキタイプのどれかに内包される概念ではなく、独立したアーキタイプとして扱われているのです。
基本的にマナ・アドバンテージの呪文を妨害するよりも、クリーチャーを除去する方が比較的容易に行えます。その事からランプデッキはマナ・クリーチャーよりも土地やアーティファクト等の恒久的なマナ加速を用いる事を原則としています。つまりこれが何を意味しているのかというと、ランプデッキが正常にランプした場合とアグロデッキが正常にカーブした場合とでは、他のアーキタイプからの干渉を受け辛いランプデッキが有利になるのが一般的だ、という事に他なりません。
その一方で、このアーキタイプには明確な欠点が2つあります。まず1つに、ランプデッキはマナ加速に特化している為、ランプカードを引きすぎても引かなすぎてもフィニッシャーたる脅威を展開する事が出来ないので、安定性に欠けるといった事が挙げられます。マナ加速の為に手札を消費してしまうので、ハンド・アドバンテージの確保や、ランプの為のソーサリー呪文にマナを割いてしまうので、インスタント・タイミングで動きにくい事も安定性を欠く要因となっています。2つ目に、このデッキは1つ、または複数の大きな脅威に依存していて、それらを達成する為に複数回のマナ加速を行いますが、それは逆説的に、その最後に着地させる脅威をカウンターされる、もしくは取り除かれてしまった場合には「ガス欠」を起こしてしまう、といった事を意味しているのです。
ランプデッキ構築の為のヒント
◆ランプデッキは初期ターンからの脅威に変え、《極楽鳥/Birds of Paradise》や《真面目な身代わり/Solemn Simulacrum》、《肥沃な大地/Fertile Ground》や《不屈の自然/Rampant Growth》、《旅人のガラクタ/Wayfarer’s Bauble》の様なランプカードからマナ・アドバンテージに差を付けていく事を基本とする。それらのランプカードはおおよそ12枚程度デッキに散りばめられており、土地は23から24枚ほど組み込まれる。
◆有効性の高い除去カードを8から12枚採用している。主だったカードは《終止/Terminate》や《マナ漏出/Mana Leak》、《原初の命令/Primal Command》など。また、《悪魔火/Demonfire》や《暴力的な根本原理/Violent Ultimatum》などの「爆弾カード」を1、2枚搭載しているデッキも散見される。
◆クリーチャーは一般的に12から16枚に抑えられており、《台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks》や《カメレオンの巨像/Chameleon Colossus》、《トロールの苦行者/Troll Ascetic》と言った全体除去や個別除去に対して耐性の高いものが見受けられる。その他のクリーチャーでは《孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth》や《原始のタイタン/Primeval Titan》の様なフィニッシャーが採用されている。
ミッドレンジデッキとは、中マナ域のクリーチャーを中心とした、ビートダウンとコントロールの中間的なデッキを指します。このデッキは、能力を持つ1マナのクリーチャー(《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》や《ルーンの母/Mother of Runes》など、小粒でありながらもそれに反して初期ターンの脅威である事は明確だと言えるクリーチャー)と、コストの低さよりも柔軟性を重視した優秀なアタッカーという2本の柱を特徴としています。
アグロ等の高速ビートダウンデッキは軽量クリーチャーに特化し、1ターン目からアタッカーを展開することを理想としていますが、それに対してミッドレンジは、初速の代わりにクリーチャー1体1体の性能を重視しています。1マナの戦闘要員をほとんど採用せず、代わりに3~6マナ域を中心とするやや重めのクリーチャーを多用する傾向にあります。1マナのクリーチャーを用いる場合、それは後続のサポート役としての意味合いが強いです。特に緑を含むミッドレンジではマナ・クリーチャーの採用が定番です。ミッドレンジのクリーチャーはクロッカーとしての役割が大きいので、クリーチャーとして求められるものは(サイズや能力的に見て)恒久的にダメージを与え続けられるかどうかが最重要とされています。
このデッキはクリーチャーなどのダメージ源を展開し、同時に土地破壊や手札破壊、カウンターなどのコントロール要素で対戦相手の動きを妨害してクロックを維持し、そのまま勝負を決めるのが基本戦略です。また、アグロデッキより展開が遅くなる(それでも適度には早い)傾向が強いですが、全体除去やプレインズウォーカーなどのボード・アドバンテージが取れるカードを優先して採用しているので、初動の遅れは取り戻しやすいといえるでしょう。
ミッドレンジの中には主要な脅威に対処するためにいくつかの対策カードを採用しているタイプがあります。その場合、この種のカードを多く引きすぎた際、それらを戦場に展開する事が出来無い(ボード・アドバンテージに直結しにくい)ため、不利になる事があります。
ミッドレンジデッキの中にはアグロ的な傾向があるものもあれば、コントロール寄りなものもあります。それらに共通するのは、少ないリソースでアドバンテージを得続ける事とは対照的に、戦場に留まり、場のアドバンテージを蓄積し続ける事に焦点を当てている事が特徴です。例えば、1枚のカードに対して2枚の手札を持つようにする(ハンド・アドバンテージを得る)のではなく、2/1クリーチャーに対して4/4クリーチャーを出しておく(ボード・アドバンテージを得る)という事です。
ウィニーとの対決では初動の遅れをクリーチャーの性能差で巻き返せるため、概ねミッドレンジ側が有利になることが多いです。その一方、コンボデッキやランプデッキに対しては手札・呪文に干渉する手段を持たない限り、ライフを0にする前に相手が目的を達成してしまうことがほとんどで、ウィニー以上に不利となる事が多いでしょう。
ミッドレンジデッキ構築の為のヒント
アグロ等の高速ビートダウンデッキは軽量クリーチャーに特化し、1ターン目からアタッカーを展開することを理想としていますが、それに対してミッドレンジは、初速の代わりにクリーチャー1体1体の性能を重視しています。1マナの戦闘要員をほとんど採用せず、代わりに3~6マナ域を中心とするやや重めのクリーチャーを多用する傾向にあります。1マナのクリーチャーを用いる場合、それは後続のサポート役としての意味合いが強いです。特に緑を含むミッドレンジではマナ・クリーチャーの採用が定番です。ミッドレンジのクリーチャーはクロッカーとしての役割が大きいので、クリーチャーとして求められるものは(サイズや能力的に見て)恒久的にダメージを与え続けられるかどうかが最重要とされています。
このデッキはクリーチャーなどのダメージ源を展開し、同時に土地破壊や手札破壊、カウンターなどのコントロール要素で対戦相手の動きを妨害してクロックを維持し、そのまま勝負を決めるのが基本戦略です。また、アグロデッキより展開が遅くなる(それでも適度には早い)傾向が強いですが、全体除去やプレインズウォーカーなどのボード・アドバンテージが取れるカードを優先して採用しているので、初動の遅れは取り戻しやすいといえるでしょう。
ミッドレンジの中には主要な脅威に対処するためにいくつかの対策カードを採用しているタイプがあります。その場合、この種のカードを多く引きすぎた際、それらを戦場に展開する事が出来無い(ボード・アドバンテージに直結しにくい)ため、不利になる事があります。
ミッドレンジデッキの中にはアグロ的な傾向があるものもあれば、コントロール寄りなものもあります。それらに共通するのは、少ないリソースでアドバンテージを得続ける事とは対照的に、戦場に留まり、場のアドバンテージを蓄積し続ける事に焦点を当てている事が特徴です。例えば、1枚のカードに対して2枚の手札を持つようにする(ハンド・アドバンテージを得る)のではなく、2/1クリーチャーに対して4/4クリーチャーを出しておく(ボード・アドバンテージを得る)という事です。
ウィニーとの対決では初動の遅れをクリーチャーの性能差で巻き返せるため、概ねミッドレンジ側が有利になることが多いです。その一方、コンボデッキやランプデッキに対しては手札・呪文に干渉する手段を持たない限り、ライフを0にする前に相手が目的を達成してしまうことがほとんどで、ウィニー以上に不利となる事が多いでしょう。
ミッドレンジデッキ構築の為のヒント
◆ミッドレンジデッキは、対戦相手が死ぬまでダメージを与え続けるという事はアグロデッキと変わらないが、アグロ以上にマナ消費が激しいカードを使用している。
◆ミッドレンジデッキはファッティーが多く、ウィニーは少ない。優秀なファッティー無しではミッドレンジデッキを構築する事は不可能である。古典的なミッドレンジ・クリーチャーは、《貪欲なるベイロス/Ravenous Baloth》と《賛美されし天使/Exalted Angel》である。
◆ミッドレンジデッキは比較的マナコストが高いカードを採用している。その中にはゲーム序盤から中盤まで試合をリード出来る様な呪文を含んでいる。ゲームが進むにつれて効果が高まる《火の玉/Fireball》のような 「スケーリング」カードをプレイするには比較的条件の良いアーキタイプである。
◆土地の枚数は22から24枚が基本的な枚数だ。ミッドレンジデッキのマナカーブは、 "アグロデッキ"よりもマナコストが高い曲線であるが、 "ランプデッキ"よりも低い曲線である。ミッドレンジデッキは効果的に呪文をプレイするために、マナ発生源をデッキスロットに十分量確保する必要がある。マナ加速やマナ蓄積装置を駆使し、余剰のマナを効果的に使うように構成されなければならない。それらのカードはデッキの中に8枚程度散らしてあることが多い。
◆ミッドレンジデッキは通常、(特にアグロデッキに対して)自分自身を守るために一つ以上の対策をしている。それにはコントロールデッキに必要不可欠な専用のボードコントロール要素、《花の壁/Wall of Blossoms》や《風生まれの詩神/Windborn Muse》の様なカードが用いられることが多い。そして時々、大量破壊的なリセットボタンを押す事もある。
◆ミッドレンジデッキが大好きな人の不滅の言葉をここに記しておく。「それが、お前を殺す最後のファッティだ。」 - Jamie Wakefield
アグロとは、"効率的なクリーチャーを使ってできるだけ早く相手を殺す"タイプの伝統的なデッキです。クリーチャーによる攻撃を中心とし、複雑なギミックを搭載しておらず、能動的に相手を攻めるデッキ、とも言い換えられます。
アグロデッキは通常、《教区の勇者/Champion of the Parish》や《ジャングル・ライオン/Jungle Lion》の様な、点数で見たマナ・コストが1~2程度のクリーチャーが強力な攻撃ベースを築き上げています。その軽さからクリーチャーのサイズは基本的に小型ですが、コストに比してサイズが大きいものも高速展開が可能であれば採用される傾向にあります。
このアーキタイプは、カードを低コスト域に集中させることにより、最初の数ターンで大量のクリーチャーを高速で展開することに重きを置いており、その第一の戦略を補完する形でマナ・カーブが用意されているのが特徴です。また、その最初の突撃が鈍った後や弱点克服、早期決着のために3マナ以上のカードを採用して、ゲームを終わらせる手段が用意されている場合もあります。
クリーチャーの採用基準としては、点数で見たマナ・コストが2以下でパワーが1~3の防衛を持っていないクリーチャーがひとつの目安とされています。また、アグロデッキは攻撃重視のデッキなので、《サマイトの癒し手/Samite Healer》のようにパワーがコストを下回るクリーチャーはあまり使用されない傾向にあります。
アグロデッキにとって「速さ」はとても重要な要素です。なぜならば他のデッキは「準備完了」するまで、ある程度ライフを削らせてくれるからです。それを上手く活用するには1ターン目から動くことが必要不可欠なのです。
アグロデッキの場合、1ターン目に火力呪文を本体へ撃ち込むよりも、1、2ターン目と続けてクリーチャーを出す方が理想的と言えるでしょう。それは第4ターン目に飛んで来るであろう《神の怒り/Wrath of God》を考えての行動からです。1マナのクリーチャーは3回、2マナのクリーチャーは2回、3マナのクリーチャーは1回、《神の怒り/Wrath of God》までに攻撃が出来ます。4マナのクリーチャーは(速攻を持っていない限り)1度も攻撃に参加することが出来ずに《神の怒り/Wrath of God》に巻き込まれてしまうでしょう。
マナコストが重くコントロール要素が強いカードは、対戦相手の手札に眠らせたままにしておくのが賢い方法です。その為には速度で相手を上回り、最短で勝負を決しなければなりません。
1ターン目に必ずと言って良い程1マナクリーチャーをプレイしたいのであれば、デッキに相当数1マナクリーチャーを入れなくてはなりません。同じような事が2マナクリーチャーにも言えるでしょう。クリーチャーの質に関しても、速さに勝るとも劣らないくらい重要な要素です。
アグロデッキは毎ターン全てのマナを使い切り、効率的にダメージを生み出す最良のシークェンスを行なう事が重要です。その為には1~2マナ域に偏った、極端なマナカーブになる事がほとんどで、3~4マナ域のカードはほとんど採用されない傾向にあります。
アグロデッキは極端にマナを消費しない構成を取っているので、コントロール等の遅いデッキよりも土地の採用枚数を減らすことが出来ます。中心となるゲームプランのほとんどは2マナで動かせる為、他のデッキより更に土地を切り詰めることが可能なのです。
対して《神の怒り/Wrath of God》を擁するコントロールデッキでは、相当数の土地を採用し、4ターン目までは確実に土地を1枚ずつ置いていき、4ターン目に確実に4マナが出ていない限り、アグロデッキに対して勝つ手段はほとんど無いと言っても良いでしょう。
マナカーブはどんなデッキにも重要な概念ですが、アグロデッキが真に焦点を当てているのは「ダメージ効率」なのです。火力はカードに書いてある数字が相手のライフを削ぎますが、クリーチャーはそうではないのです。盤面によって与えられるダメージが変わってくる為、クリーチャーのダメージ効率を評価する事は困難でしょう。
アグロデッキを扱うにあたり、クリーチャーに迅速かつ効率的なダメージディーラーとして働いてもらうには、デッキを構築した時点で自分がどのようにクリーチャーに仕事をしてもらうかをしっかり思い描けており、また火力をどの程度「除去」として使えるだけ搭載しているのかを把握出来ているかが重要になってきます。
クリーチャーでダメージを与えるという事は、例えばパワー2のクリーチャーで3回「攻撃できたとしたら」その合計値は6になり、2回しか攻撃できなかった場合は4となります。攻撃できずに除去されてしまった場合は0です。それに比べ、火力の場合は書いてある数字の通り(《稲妻/Lightning Bolt》なら3点)のダメージを生み出します。これはそれ以上にもならず、それ以下にもならないという事に他なりません。
自分が2/2クリーチャーをコントロールしていて、相手が3/3クリーチャーをコントロールしており、自分の手札には《稲妻/Lightning Bolt》がある場合の話をしましょう。ダメージ効率を求めるのであれば対戦相手に《稲妻/Lightning Bolt》を撃ち込むのが正解です。しかし、2/2クリーチャーが確実に4ダメージ、すなわち2回攻撃できる状況なのであれば、3/3クリーチャーを除去するために《稲妻/Lightning Bolt》を使うべきだと言う事です。
アグロデッキは対戦相手がどんなデッキを使い、どんなカードを使っていたとしても、毎回行なうシークェンスはそう大きく変わりません。コンボデッキやコントロールデッキと違って、各々のカードの行う仕事は「ダメージを与える」と言う事だけで、機能的には全く変わりがありません。クリーチャー呪文とダメージ呪文は表面的に共通点はほとんどありませんが、カードが行った仕事の最終的結果はほぼ同じです。そう、「ダメージを与えた」だけなのです。
恒久的なダメージを与えられるもの以外のパーマネント(オーラ等)は、メタゲーム等を考慮せずに投入するのは控えるべきでしょう。なぜならばアグロデッキはダメージ効率を最優先するべきであって、ボード・コントロール力やその他のアドバンテージは全てに於いて2の次だからです。
【アグロデッキ構築の為のヒント】
アグロデッキは通常、《教区の勇者/Champion of the Parish》や《ジャングル・ライオン/Jungle Lion》の様な、点数で見たマナ・コストが1~2程度のクリーチャーが強力な攻撃ベースを築き上げています。その軽さからクリーチャーのサイズは基本的に小型ですが、コストに比してサイズが大きいものも高速展開が可能であれば採用される傾向にあります。
このアーキタイプは、カードを低コスト域に集中させることにより、最初の数ターンで大量のクリーチャーを高速で展開することに重きを置いており、その第一の戦略を補完する形でマナ・カーブが用意されているのが特徴です。また、その最初の突撃が鈍った後や弱点克服、早期決着のために3マナ以上のカードを採用して、ゲームを終わらせる手段が用意されている場合もあります。
クリーチャーの採用基準としては、点数で見たマナ・コストが2以下でパワーが1~3の防衛を持っていないクリーチャーがひとつの目安とされています。また、アグロデッキは攻撃重視のデッキなので、《サマイトの癒し手/Samite Healer》のようにパワーがコストを下回るクリーチャーはあまり使用されない傾向にあります。
アグロデッキにとって「速さ」はとても重要な要素です。なぜならば他のデッキは「準備完了」するまで、ある程度ライフを削らせてくれるからです。それを上手く活用するには1ターン目から動くことが必要不可欠なのです。
アグロデッキの場合、1ターン目に火力呪文を本体へ撃ち込むよりも、1、2ターン目と続けてクリーチャーを出す方が理想的と言えるでしょう。それは第4ターン目に飛んで来るであろう《神の怒り/Wrath of God》を考えての行動からです。1マナのクリーチャーは3回、2マナのクリーチャーは2回、3マナのクリーチャーは1回、《神の怒り/Wrath of God》までに攻撃が出来ます。4マナのクリーチャーは(速攻を持っていない限り)1度も攻撃に参加することが出来ずに《神の怒り/Wrath of God》に巻き込まれてしまうでしょう。
マナコストが重くコントロール要素が強いカードは、対戦相手の手札に眠らせたままにしておくのが賢い方法です。その為には速度で相手を上回り、最短で勝負を決しなければなりません。
1ターン目に必ずと言って良い程1マナクリーチャーをプレイしたいのであれば、デッキに相当数1マナクリーチャーを入れなくてはなりません。同じような事が2マナクリーチャーにも言えるでしょう。クリーチャーの質に関しても、速さに勝るとも劣らないくらい重要な要素です。
アグロデッキは毎ターン全てのマナを使い切り、効率的にダメージを生み出す最良のシークェンスを行なう事が重要です。その為には1~2マナ域に偏った、極端なマナカーブになる事がほとんどで、3~4マナ域のカードはほとんど採用されない傾向にあります。
アグロデッキは極端にマナを消費しない構成を取っているので、コントロール等の遅いデッキよりも土地の採用枚数を減らすことが出来ます。中心となるゲームプランのほとんどは2マナで動かせる為、他のデッキより更に土地を切り詰めることが可能なのです。
対して《神の怒り/Wrath of God》を擁するコントロールデッキでは、相当数の土地を採用し、4ターン目までは確実に土地を1枚ずつ置いていき、4ターン目に確実に4マナが出ていない限り、アグロデッキに対して勝つ手段はほとんど無いと言っても良いでしょう。
マナカーブはどんなデッキにも重要な概念ですが、アグロデッキが真に焦点を当てているのは「ダメージ効率」なのです。火力はカードに書いてある数字が相手のライフを削ぎますが、クリーチャーはそうではないのです。盤面によって与えられるダメージが変わってくる為、クリーチャーのダメージ効率を評価する事は困難でしょう。
アグロデッキを扱うにあたり、クリーチャーに迅速かつ効率的なダメージディーラーとして働いてもらうには、デッキを構築した時点で自分がどのようにクリーチャーに仕事をしてもらうかをしっかり思い描けており、また火力をどの程度「除去」として使えるだけ搭載しているのかを把握出来ているかが重要になってきます。
クリーチャーでダメージを与えるという事は、例えばパワー2のクリーチャーで3回「攻撃できたとしたら」その合計値は6になり、2回しか攻撃できなかった場合は4となります。攻撃できずに除去されてしまった場合は0です。それに比べ、火力の場合は書いてある数字の通り(《稲妻/Lightning Bolt》なら3点)のダメージを生み出します。これはそれ以上にもならず、それ以下にもならないという事に他なりません。
自分が2/2クリーチャーをコントロールしていて、相手が3/3クリーチャーをコントロールしており、自分の手札には《稲妻/Lightning Bolt》がある場合の話をしましょう。ダメージ効率を求めるのであれば対戦相手に《稲妻/Lightning Bolt》を撃ち込むのが正解です。しかし、2/2クリーチャーが確実に4ダメージ、すなわち2回攻撃できる状況なのであれば、3/3クリーチャーを除去するために《稲妻/Lightning Bolt》を使うべきだと言う事です。
アグロデッキは対戦相手がどんなデッキを使い、どんなカードを使っていたとしても、毎回行なうシークェンスはそう大きく変わりません。コンボデッキやコントロールデッキと違って、各々のカードの行う仕事は「ダメージを与える」と言う事だけで、機能的には全く変わりがありません。クリーチャー呪文とダメージ呪文は表面的に共通点はほとんどありませんが、カードが行った仕事の最終的結果はほぼ同じです。そう、「ダメージを与えた」だけなのです。
恒久的なダメージを与えられるもの以外のパーマネント(オーラ等)は、メタゲーム等を考慮せずに投入するのは控えるべきでしょう。なぜならばアグロデッキはダメージ効率を最優先するべきであって、ボード・コントロール力やその他のアドバンテージは全てに於いて2の次だからです。
【アグロデッキ構築の為のヒント】
◆アグロデッキは一般的に、自分のライフの総量を完全に無視し、相手が死ぬまでダメージを与え続ける事を戦略としている。
◆アグロデッキに投入されているカードの大半は、対戦相手にトドメをさせるカードである。
◆アグロデッキは通常、1マナと2マナのカードがそれぞれ8~12枚ずつ投入されている。
◆アグロデッキは通常、23枚以下の少ない土地、または非攻撃マナ源を採用している。
◆サイズの小さいクリーチャーを初期ターンから攻撃に向かわせると、たった1枚のカードで少なくとも火力呪文と同等のダメージを与える事が出来る。
◆アグロデッキの呪文は、ダメージ / 除去呪文(《稲妻/Lightning Bolt》)、パンプアップ呪文(《怨恨/Rancor》や《粗暴な力/Brute Force》)、積極的なカードアドバンテージ呪文(《獣群の呼び声/Call of the Herd》や《絡み根の霊/Strangleroot Geist》)などで構成されている。
やぁみんな、久し振り。今僕はちょっとやるべき事があって、なかなかコッチに来られない状況なんけど、とてもすごく気になる日記がアップされててね。きっと僕がコレには応えなくちゃいけないんだと思って筆を執っているよ。
それはどんな日記だったか、だって?実はそれはあまり関係ないんだ。それは実際、僕が筆を執るきっかけになっただけに過ぎないからね。とりとめて騒ぐ必要も無い事だよ。僕の中ではとてもすごく重要だけど、これからコレを読む君達には、これから僕が伝えようとしている事の方が重要だ。
前置きが長くなってしまって申し訳ない、僕の悪い癖だ。さぁ、始めようか。
そもそも、僕達「カジュアル・クラシッカー」、大雑把に括ってMTGを「趣味」として「嗜んでいる」人達にとって何より重要なのが「デッキ」だ。それはもう自分自身の「作品」といっても過言ではないし、差し支えないと思う。
だって考えてもみてくれ。膨大なカードの中からたった75枚の組み合わせを考える。それって数限りなくパターンがある訳だし、多分きっと、組み上げる人の「個性」がそのまま反映されるものだから。それが作品以外の何物であろうか。きっと、僕をはじめとするカジュアル・クラシッカーはみんなそう考えている筈だ。
だから僕達は「新たなるアーキタイプの構築」を指針にMTGを嗜んでいる。環境に対するソリューションを導きだすのではなく、どれだけ「人とは違った視点でMTGを考察出来ているか」を重点にデッキを組み上げる。(まぁ、これは僕がジョニーである部分が大半だとは思うんだけどね。)
デッキを組み上げる上での最優先事項は「今までに無いデッキタイプかどうか」って事だ。例えば僕達が《梅澤の十手/Umezawa’s Jitte》を使わないのはそういった理由からだ。決して「高くて手が出ないから」じゃなく、このカード1枚で戦場を制圧出来てしまう上に、どのビートダウンデッキにも入りうる上、一度でも戦場に出たらそれはもう「十手デッキ」になってしまい、デッキの個性を殺してしまうと言った事がこのカードを採用しない最たる理由だ。
カジュアル・クラシッカーにも色々なタイプがいるけれども、この部分だけはみんなが共通して持っている認識だと思う。そしてそれが「つまらない」に繋がってくるんだ。なぜソレがつまらないに繋がってくるのか。それは「勝ちよりも価値のある事がそこにはあるから」なんだ。
僕達は「勝つ為にMTGをやっている」わけじゃない。僕達は「MTGをやるからには勝つ」んだ。高いカードや一般的に強いとされているカードを使わなくても、それは勝ちから逃げている事とイコールには決してならない。だからパワーカードを嫌う傾向にあるね。簡単に勝ちを得られるってこともそうだけど、だってそのカードはもう「強い」って証明されているからね。僕達はまだ見ぬシナジーや、見向きもされていないカードを表舞台に上げてあげる事を喜びと感じるんだ。それが、僕達の「遊び方」だよ。
コントロールの確立された戦場で暴れ回る《練達の変成者/Master Transmuter》の強さに一喜一憂したり、マナ・ランプからの後攻3ターン目《明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star》着地からのサクリファイスだったり、僕達はそっちの方が「勝つ事よりも楽しい」と思えるんだ。だって、そんな動き今まで見た事が無いんだもの!見た事の無い動きは新鮮で、いつも僕達に期待と不安を同量与えてくれる。これからどんな動きをするのか、そんなすごい動きをするデッキに僕の作ったデッキは勝てるのか、ってな具合にね。それが何より楽しいんだ!
…でもやっぱり高いカードに勝つ事は難しいのは事実。みんながみんな、この「カジュアル・クラシック」でプレイしている訳じゃないからね。でも、そこからが僕達の真骨頂だ!素直に諦めて高いカードを使う?そんな事するくらいなら始めからこんなデッキは使わない!だったらどうするのか?そう、考えて、上手くなるんだ。(ちなみに君が上手くなりたいと思っているなら僕はいくらでも協力するからいつでも言ってくれ。)
例えば。簡単な話をしようか。
①《耕作/Cultivate》を含むマナ・ランプを12枚程度投入して、ランプデッキを構築するとしよう。そうだね、フィニッシャーは《無限のワーム/Endless Wurm》がいい。コイツは《怨恨/Rancor》と恐ろしい程のシナジーをもたらす。11/9、しかもトランプルを持った化物が毎ターンたった緑1マナで使役出来るのは凄いね。
②また、ランプデッキは想像以上に手札を消費する。その為に《よりよい品物/Greater Good》を入れよう。差し引き9枚のカードを得られるし、《怨恨/Rancor》は手札に戻る。インスタントタイミングの除去に合わせてサクリファイス出来ると強そうだね。
③うーん、これだと後半にはマナが大きく余りそうだね。それじゃあ《世界棘のワーム/Worldspine Wurm》を入れてみよう!《よりよい品物/Greater Good》とのシナジーも期待出来るし、追放以外の除去であれば、ボードアドバンテージがとれそうだ。なかなかいい感じになってきた。
④それでもやっぱり追放系のスペルが怖いね。だったら《巨森の蔦/Vines of Vastwood》の出番だ!相手の呪文を回避しながら強化も出来る優れもの。コレを生かす為にはプレイングも重要そうだね。《無限のワーム/Endless Wurm》と《怨恨/Rancor》、それに《巨森の蔦/Vines of Vastwood》の計7マナになるまではマナ加速に徹底した方が良さそうだ。
⑤そうするとランプカードのカウンターが怖いね。だったら《すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All》だ。幸い緑には土地をサーチするカードが豊富にある。その辺も含めてランプカードとの兼ね合いをとっていけば仕上がりそうだね。
とまぁこんな感じかな。本来ならもっと詰めなきゃならないけど、これだけでも意味合いを感じ取ってもらえると思う。僕達はこういった様にデッキを構築していく。多分慣れていない人は①しか思いつけないんだと思う。僕を含めたカジュアル・クラシッカーは、「その筋」で長年やってきているからこうパッと思いついたり出来るんだけど、多分嘆いている人達は①で止まってしまっているのだと思うよ。
特に④。自分のデッキの弱点とそれに対応出来るカードとプレイング。この部分がしっかりしていないとやっぱり勝つ事は難しいかな。これは慣れしかない。
話は変わるけど、僕にはライバルと呼べる人が一人と、カジュアル・クラシックをやっているメイドさんが1人いる。そのメイドさんも①は結構しっかりしているんだけれども、それ以外が薄い感じ。だから僕が余計なお世話かもしれないけれども、アドバイスをしてる。もちろん、本人の見つけた「デッキの種」を殺さない様なカードを教えているよ。自慢じゃないけれども、実際それでものすごく強くなって、僕も勝てないくらいのデッキに仕上がったものもある。
そのメイドさんの凄い所は「負けてもめげない」って事。負けたとしても文句なんて絶対にいわないし、何より所謂「札束デッキ」に当たったとしても「自分の使ってるカードが安かったから負けた」とはいわず、「自分がデッキを使いこなせていないから」と考えるのが素晴らしい。そして、「負けから次の一手を見いだす」って事を常にやっているね。勝つ事よりも、むしろ負ける事に意味を見いだしているよ。勝負して負けるたびにやる「反省会」も、僕にとっては楽しみの一つになっているよ。それもカジュアル・クラシックの楽しみ方の一つのうちに数えても良いかもしれないね。
そんな僕のメイドさんの好きな言葉を二つ挙げておこうと思う。
「疑え。もう1回疑え。あと1回疑え。最後に1回疑え。」
「手は綺麗に、心は熱く、頭は冷静に。」
これをモットーに、「カジュアル・クラシック」なスタイルであれば、MTGに限らず、どの場面でも有効に働いてくれると思うよ。自己批判しろ、って歌もあるくらいだしね。←
ある人はこの「カジュアル・クラシック」って概念について「他人に伝える事はそんなに難しいとは思わない」と言っていたけれど、僕はとても尊く、理解するのは難しいと思っているよ。時には住み分ける事もお互いにとって重要なんじゃないかな。気持ちだけ先に行ってしまって、結局お互いに駄目になるのは人付き合いの延長上にある恋愛も一緒。そういう事だと僕は考えているよ。
そんな感じ。あんまり言いたく無いけれど、頼ってくれれば僕はいつでも出るよ。僕の方が年下だけど、この概念については僕の方が先輩だと思うし、なによりここには書かない様な「経験値」が僕を後押ししてくれてるからね。だからいつでもどうぞ。
それはどんな日記だったか、だって?実はそれはあまり関係ないんだ。それは実際、僕が筆を執るきっかけになっただけに過ぎないからね。とりとめて騒ぐ必要も無い事だよ。僕の中ではとてもすごく重要だけど、これからコレを読む君達には、これから僕が伝えようとしている事の方が重要だ。
前置きが長くなってしまって申し訳ない、僕の悪い癖だ。さぁ、始めようか。
そもそも、僕達「カジュアル・クラシッカー」、大雑把に括ってMTGを「趣味」として「嗜んでいる」人達にとって何より重要なのが「デッキ」だ。それはもう自分自身の「作品」といっても過言ではないし、差し支えないと思う。
だって考えてもみてくれ。膨大なカードの中からたった75枚の組み合わせを考える。それって数限りなくパターンがある訳だし、多分きっと、組み上げる人の「個性」がそのまま反映されるものだから。それが作品以外の何物であろうか。きっと、僕をはじめとするカジュアル・クラシッカーはみんなそう考えている筈だ。
だから僕達は「新たなるアーキタイプの構築」を指針にMTGを嗜んでいる。環境に対するソリューションを導きだすのではなく、どれだけ「人とは違った視点でMTGを考察出来ているか」を重点にデッキを組み上げる。(まぁ、これは僕がジョニーである部分が大半だとは思うんだけどね。)
デッキを組み上げる上での最優先事項は「今までに無いデッキタイプかどうか」って事だ。例えば僕達が《梅澤の十手/Umezawa’s Jitte》を使わないのはそういった理由からだ。決して「高くて手が出ないから」じゃなく、このカード1枚で戦場を制圧出来てしまう上に、どのビートダウンデッキにも入りうる上、一度でも戦場に出たらそれはもう「十手デッキ」になってしまい、デッキの個性を殺してしまうと言った事がこのカードを採用しない最たる理由だ。
カジュアル・クラシッカーにも色々なタイプがいるけれども、この部分だけはみんなが共通して持っている認識だと思う。そしてそれが「つまらない」に繋がってくるんだ。なぜソレがつまらないに繋がってくるのか。それは「勝ちよりも価値のある事がそこにはあるから」なんだ。
僕達は「勝つ為にMTGをやっている」わけじゃない。僕達は「MTGをやるからには勝つ」んだ。高いカードや一般的に強いとされているカードを使わなくても、それは勝ちから逃げている事とイコールには決してならない。だからパワーカードを嫌う傾向にあるね。簡単に勝ちを得られるってこともそうだけど、だってそのカードはもう「強い」って証明されているからね。僕達はまだ見ぬシナジーや、見向きもされていないカードを表舞台に上げてあげる事を喜びと感じるんだ。それが、僕達の「遊び方」だよ。
コントロールの確立された戦場で暴れ回る《練達の変成者/Master Transmuter》の強さに一喜一憂したり、マナ・ランプからの後攻3ターン目《明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star》着地からのサクリファイスだったり、僕達はそっちの方が「勝つ事よりも楽しい」と思えるんだ。だって、そんな動き今まで見た事が無いんだもの!見た事の無い動きは新鮮で、いつも僕達に期待と不安を同量与えてくれる。これからどんな動きをするのか、そんなすごい動きをするデッキに僕の作ったデッキは勝てるのか、ってな具合にね。それが何より楽しいんだ!
…でもやっぱり高いカードに勝つ事は難しいのは事実。みんながみんな、この「カジュアル・クラシック」でプレイしている訳じゃないからね。でも、そこからが僕達の真骨頂だ!素直に諦めて高いカードを使う?そんな事するくらいなら始めからこんなデッキは使わない!だったらどうするのか?そう、考えて、上手くなるんだ。(ちなみに君が上手くなりたいと思っているなら僕はいくらでも協力するからいつでも言ってくれ。)
例えば。簡単な話をしようか。
①《耕作/Cultivate》を含むマナ・ランプを12枚程度投入して、ランプデッキを構築するとしよう。そうだね、フィニッシャーは《無限のワーム/Endless Wurm》がいい。コイツは《怨恨/Rancor》と恐ろしい程のシナジーをもたらす。11/9、しかもトランプルを持った化物が毎ターンたった緑1マナで使役出来るのは凄いね。
②また、ランプデッキは想像以上に手札を消費する。その為に《よりよい品物/Greater Good》を入れよう。差し引き9枚のカードを得られるし、《怨恨/Rancor》は手札に戻る。インスタントタイミングの除去に合わせてサクリファイス出来ると強そうだね。
③うーん、これだと後半にはマナが大きく余りそうだね。それじゃあ《世界棘のワーム/Worldspine Wurm》を入れてみよう!《よりよい品物/Greater Good》とのシナジーも期待出来るし、追放以外の除去であれば、ボードアドバンテージがとれそうだ。なかなかいい感じになってきた。
④それでもやっぱり追放系のスペルが怖いね。だったら《巨森の蔦/Vines of Vastwood》の出番だ!相手の呪文を回避しながら強化も出来る優れもの。コレを生かす為にはプレイングも重要そうだね。《無限のワーム/Endless Wurm》と《怨恨/Rancor》、それに《巨森の蔦/Vines of Vastwood》の計7マナになるまではマナ加速に徹底した方が良さそうだ。
⑤そうするとランプカードのカウンターが怖いね。だったら《すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All》だ。幸い緑には土地をサーチするカードが豊富にある。その辺も含めてランプカードとの兼ね合いをとっていけば仕上がりそうだね。
とまぁこんな感じかな。本来ならもっと詰めなきゃならないけど、これだけでも意味合いを感じ取ってもらえると思う。僕達はこういった様にデッキを構築していく。多分慣れていない人は①しか思いつけないんだと思う。僕を含めたカジュアル・クラシッカーは、「その筋」で長年やってきているからこうパッと思いついたり出来るんだけど、多分嘆いている人達は①で止まってしまっているのだと思うよ。
特に④。自分のデッキの弱点とそれに対応出来るカードとプレイング。この部分がしっかりしていないとやっぱり勝つ事は難しいかな。これは慣れしかない。
話は変わるけど、僕にはライバルと呼べる人が一人と、カジュアル・クラシックをやっているメイドさんが1人いる。そのメイドさんも①は結構しっかりしているんだけれども、それ以外が薄い感じ。だから僕が余計なお世話かもしれないけれども、アドバイスをしてる。もちろん、本人の見つけた「デッキの種」を殺さない様なカードを教えているよ。自慢じゃないけれども、実際それでものすごく強くなって、僕も勝てないくらいのデッキに仕上がったものもある。
そのメイドさんの凄い所は「負けてもめげない」って事。負けたとしても文句なんて絶対にいわないし、何より所謂「札束デッキ」に当たったとしても「自分の使ってるカードが安かったから負けた」とはいわず、「自分がデッキを使いこなせていないから」と考えるのが素晴らしい。そして、「負けから次の一手を見いだす」って事を常にやっているね。勝つ事よりも、むしろ負ける事に意味を見いだしているよ。勝負して負けるたびにやる「反省会」も、僕にとっては楽しみの一つになっているよ。それもカジュアル・クラシックの楽しみ方の一つのうちに数えても良いかもしれないね。
そんな僕のメイドさんの好きな言葉を二つ挙げておこうと思う。
「疑え。もう1回疑え。あと1回疑え。最後に1回疑え。」
「手は綺麗に、心は熱く、頭は冷静に。」
これをモットーに、「カジュアル・クラシック」なスタイルであれば、MTGに限らず、どの場面でも有効に働いてくれると思うよ。自己批判しろ、って歌もあるくらいだしね。←
ある人はこの「カジュアル・クラシック」って概念について「他人に伝える事はそんなに難しいとは思わない」と言っていたけれど、僕はとても尊く、理解するのは難しいと思っているよ。時には住み分ける事もお互いにとって重要なんじゃないかな。気持ちだけ先に行ってしまって、結局お互いに駄目になるのは人付き合いの延長上にある恋愛も一緒。そういう事だと僕は考えているよ。
そんな感じ。あんまり言いたく無いけれど、頼ってくれれば僕はいつでも出るよ。僕の方が年下だけど、この概念については僕の方が先輩だと思うし、なによりここには書かない様な「経験値」が僕を後押ししてくれてるからね。だからいつでもどうぞ。
Primer Decks:Zombies!!!
2014年3月18日 MTG Article
Primer Decks:Zombies!!!
【脳味噌が食べられてしまう前に。】
みなさんは「ゾンビ」と聞くと何を思い浮かべますか?ある人は『倒しても倒しても何度も蘇る』と言うでしょう。またある人は『群れで襲いかかってくる』とも。少ない意見で言えば『死体が合体して、1つの巨大なゾンビになるんだ!』なんてのもあったりします。
よろしい、全て叶えましょう!このデッキにはその全ての要素が入っています。ゾンビ達は倒されても倒されても墓地や手札から何度も蘇り、対戦相手に群れで襲いかかります。そして死体が「補充」された暁には、巨大なゾンビの王が戦場に降臨するのです!
このデッキはそういった「フレイバー」を重視して作られていますが、実力は相当なモノです。自信を持ってオススメ出来るデッキに仕上がっています。このデッキを使った貴方はその強さと、醜くも美しい耽美なるゾンビの世界に魅了されてしまう事でしょう。
また、このデッキの名前はインスピレーションを受けた同名のボードゲームから付けさせてもらいました。単純なルールで皆で盛り上がる事の出来る、素晴らしい「バカゲー(賞賛の言葉です)」になっているので、機会があったら是非プレイしてみて下さい。
…おや?そうこうしている間にも向こうからやって来てくれたみたいですよ。聞こえてきたでしょう、彼らの呻き声が。ほら、貴方の後ろにも…!
【デッキリスト】
【各カードの解説】
◆ 土地 / Lands
《沼/Swamp》
このデッキの(仕事をする上での)平均マナコストは何と「1.37」です。その事実がこの土地の少なさを裏付けています。土地の採用枚数が合計で17枚と言うのは、通常のアグロデッキと比べても少ない枚数ですが、その中でも安定してマナを出せる基本地形が14枚しかないと言う事は、逆を言えばそれ以外のカードはマナを発生させる以外の「何らかの仕事」を行うと言う事です。時に十分な枚数の土地を引けない事があるかもしれませんが、このデッキは基本的に土地が1枚あればデッキが動くように作られています。少ないマナを有効活用し、活路を見出してください。
《邪悪な岩屋/Unholy Grotto》
墓地にあるゾンビをライブラリートップに戻すカードです。主にシナジーを形成するのは《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》ですが、その他のカードとも相性は良好です。しかしながら、この土地カードからは無色のマナしか生成する事が出来ないので、土地として換算するには少し不安が残ります。と、言うのも、このデッキに採用しているほとんどのカードは無色のマナを必要としないからです。初手でこの土地をキープする場合には気をつけてください。
《ボジューカの沼/Bojuka Bog》
メインボードから気軽に採用出来る墓地対策カードです。タップインなのでテンポロスになってしまいますが、2枚目以降の「沼」とみるならば、なかなかにいい働きだと思います。対戦相手を対象に取る事が出来なかった場合には自分の墓地を対象に取らざるを得ないので、出すタイミングには気をつけてください。
◆ クリーチャー / Creatures
《カーノファージ/Carnophage》
メインアタッカーです。安定した使役には多少の痛みが伴いますが、それを感じさせない程パワフルな働きをしてくれるでしょう。このクリーチャーもそうですが、このデッキは「2点ダメージを相手本体に10回叩き込む」というプランで成り立っています。1体1体の役割を冷静に見極め、生贄に捧げるかブロッカーにするか、はたまたアタッカーにするのかを的確に指示してあげていって下さい。(何と言っても、この子達には「脳味噌」が無いですからね。)
《戦墓のグール/Diregraf Ghoul》
コチラもこのデッキを代表するメインアタッカーです。一度戦場に出てしまえば《カーノファージ/Carnophage》よりも優秀なので、採用枚数は4枚となっています。タップインが少し煩わしいですが、このデメリットが敗因に繋がることは稀でしょう。また、このデッキのウィニークリーチャー達は全て「使い捨て」と考えて下さい。土地の項目にも少し書きましたが、このデッキは土地の枚数が極端に少なく構成されています。ドローしてくるカードのほとんどは盤面に有効に働くカード達なので、上手に使って試合を有利に進めていって下さい。
《肉占い/Sarcomancy》
コレ自体はエンチャントですが、真の所、このカードは優秀な「ウィニークリーチャー」です。このデッキに関して言えば、デメリットはほぼ感じられないでしょう。1ターン目から2/2クリーチャーを着地させる事が出来るデッキは、そう多くはありません。ゲーム序盤から相手のライフを果敢に攻め、常にライフに於いて優位に立てている様な展開が望ましいですね。
《墓所這い/Gravecrawler》
このデッキのメインエンジンになります。墓地から蘇る事によって《肉占い/Sarcomancy》のデメリットを帳消しにしたり、《陰謀団式療法/Cabal Therapy》のフラッシュバックコストに充てたり、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》に自身を食べさせて彼を成長させたりと、使い方に関しては枚数に暇が無いです。ただしブロックに回る事は出来ないので、相手に対処出来ない程のファッティが出て来た場合は、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》の餌となり、彼を育てる「餌」として尽力して下さい。
《屍肉喰らい/Carrion Feeder》
このデッキのメインエンジンその2です。陰鬱の達成や探索カウンターを乗せる等、この子の行える仕事は多岐に渡ります。また、この子はデッキに入っているクリーチャーの中でも一番の成長株で、上手く育て上げることが出来ればそのサイズは、かのエムラクールすら超えることが出来ることでしょう。カジュアル・クラシックに限った事では無いですが、この子を中心に動く事が出来れば、相手の《剣を鍬に/Swords to Plowshares》や《流刑への道/Path to Exile》をかわす事が容易になります。タイミングを見極めて上手に避けましょう。
《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》
死体を寄せ集める事によって降臨するゾンビの王様です。単体のサイズで見れば、このデッキの中で最大のサイズを持ったクリーチャーです。クリーチャー同士の戦闘に於いて、5/5という巨大なサイズのクリーチャーが落とされる事はまず無いと言っても過言では無いでしょう。バウンス呪文や明滅呪文に弱いという欠点はありますが、それを差し引いたとしても有り余るスピードと火力が対戦相手を恐怖のドン底に叩き落とすでしょう。何せこの王様が着地するのには1マナしか必要としないのですから。
《血の公証人/Blood Scrivener》
このデッキはしばしば手札が無い事に悩まされます。それを逆手に取り、アドバンテージに変えてしまうのがこの子の仕事です。レガシープレイヤーには痛くない《闇の腹心/Dark Confidant》と言えば理解が早いかと思います。この子が無事に着地出来たとしたら、圧倒的なドロー加速と驚異の展開力で、場をゾンビの群れで満たしてあげましょう。腐っても(とは言いつつも、元々身体は腐ってはいますが)サイズは2/1、しっかりとクロックも刻める憎いヤツです。
《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
この子はとにかく仕事が出来る子です。場に出て仕事をして、一度墓地に落ちて仕事をして、場に戻って来て仕事をして、クロックを刻んで仕事をして、また墓地に行って仕事をして…。日本人も尻尾を巻いて逃げ出す程のハードワーカーです。柔軟性に富んだユーティリティカードだと言う事に間違いは無いのですが、黒マナを3つも使う為、少し場に出にくく感じるのが残念な所です。しかし、一度場に出てさえしまえば必要最低限の仕事はこなしているので、出せる場面では積極的に狙って行きましょう。
◆ 呪文 / Spells
《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
相手のカードを狙い撃ちして落とせるスナイパーカードです。使いこなす為には相当量の知識が伴いますが、2ゲーム目以降であれば比較的容易に狙い落とせるでしょう。基本的には《神の怒り/Wrath of God》の様な全体除去を叩き落とす為に使いますが、黒という色の特性上アーティファクトとエンチャントに触りにくい為、それらのカードを落とすのにも使えます。クリーチャーが墓地に落ちる事をトリガーとするカードが場に出ている場合は、即座にフラッシュバックを使用し、2回続けて撃って行きましょう。カードを2枚使用してしまいますが、相手の手札で最も撃たれたくないカードを確実に落とせます。
《強迫/Duress》
覚えておいて欲しいのが、このデッキは比較的多めにクリーチャー除去が搭載されていますが、クリーチャー以外のカードに積極的干渉が出来るのは、ハンデスカードを除くと《冬の宝珠/Winter Orb》だけということです。クリーチャー以外の呪文は、撃たれる前に墓地に送ってあげましょう。ゲーム序盤に撃てればほぼ間違い無く何かしらのカードが落せると思います。そして、何と言っても「相手の手札が見えている状況」というのは潜在的アドバンテージを内包しており、カードを使用する順番や除去の使い道など、コチラの戦略を遂行する上でかなり有効に働く事が多いです。また、相手のカウンター呪文を誘えたりもするので、ゲーム中盤から後半に引いてきても腐りにくいカードと言えるでしょう。
《四肢切断/Dismember》
スーサイド要素の強い、低コストの除去カードです。-5/-5に耐えうるクリーチャーはまずいないでしょう。ライフ4点の損失はかなり手痛いですが、構えておくマナが1マナで良いと言うのは、テンポの面から見ても大変優れているカードと言えます。基本的に1マナで撃つ事になるカードなので、残りライフには常に気を付けていて下さい。相手のメインクロッカーを落としつつ、コチラのクリーチャーを通す為に使うので、基本的にはミッドレンジ(目安として3/3)以上のクリーチャーに使うように心掛けていってください。
《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
陰鬱を達成すると落とせないカードはほとんど無くなる、優秀な除去呪文です。基本的には相手のシステムクリーチャーを排除する為に使いますが、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》との相性は抜群で、自分の好きなタイミングで陰鬱を達成させ、フィニッシャー級の重量クリーチャーをも落とす事が可能になります。コチラも1マナ構えていればいつでも撃てるので、《四肢切断/Dismember》と合わせてブラフが機能します。時には自殺覚悟のチャンプアタックをしてみても面白いかもしれませんね。
《血の署名/Sign in Blood》
残り2点を削り取る、フィニッシャーにもなり得るドローカードです。自分の手札が少ない場合にはドローソースとして機能し、相手のライフが少ない場合にはダメージソースとして機能します。このカードの実力はかなりのもので、本来ならば4枚搭載したい所です。しかしながらこのカード唯一の弱点として「テンポロス」が挙げられます。この唯一の弱点が、速さが重要視されるアグロデッキにとっては何とも致命的で、マナを切り詰めているこのデッキにとっては更に明確な弱点となってしまいます。言い過ぎかもしれませんが、「1ターンを無駄にしてカードを2枚得る」と言っても差し支えないと思っています。アグロデッキの1ターンは何物にも代え難いもので、テンポを崩してまでカードが欲しい事は稀です。それに、このデッキには他にもドローソースが存在しているので、このカードが輝ける場面はそこまで多くはありません。なので、この枚数に落ち着きました。アーキタイプによって搭載枚数に差が出る良い例ですね。
《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
ドローをしながら相手のライフを攻められる一人二役のカードです。マナコストを見てもらえば分かる通り、このカードが場に出る事はまずありえません。サイクリング能力を目当てに使っていきます。なので「呪文」の項目に当て込みました。ドローをしながら(平均的に)2点のライフロスを狙えるのは強い動きだと思います。また、場に《邪悪な岩屋/Unholy Grotto》が出ていれば、無限回収も出来ます。インスタントタイミングで使用可能かつ打ち消されにくいので、状況を見極めて使ってあげてください。
《冬の宝珠/Winter Orb》
このデッキの中では少し異色に映るかもしれませんが、このカードはこのデッキにピタリと当てはまります。基本的に1マナで動けるデッキなので、アンタップ制限が他のデッキと比べて苦にならない事が多いのです。そして、このデッキが苦手とする「ミッドレンジ」は、全体除去を搭載している傾向が強いです。もしも全体除去を撃たれたとしても、このカードが場に出ていれば、リカバリーまでの時間を稼ぎ出してくれる事でしょう。過去に存在した強力なアーティファクトの力を存分に味わって下さい。
◆ サイドボード / Sideboards
サイドボードの概念は別項目で解説するので、ここでは採用傾向を簡単にお伝えします。説明しなくても既にご存知だとは思いますが、このデッキのアーキタイプは「アグロ」です。一般的にこのアーキタイプは「コントロール」や「撹乱的アグロ」に強く、「ミッドレンジ」や「コンボ」に弱いです。なので、その部分を補える様にカードを選びました。しかし、一概にはそうとは言えませんので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。また、カジュアル・クラシックではレガシーやモダンと違い、文字通り「無数」のデッキタイプが存在しています。なので必然的にサイドボードは「丸く」なります。その点も併せてご覧ください。
《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt》
何はともあれ墓地対策です。短期決戦型のこのデッキでは、1回でも相手の墓地を空にする事が出来れば、その隙を突き、勝利を掴み取ることができるでしょう。マナが全くかからない事もこのデッキにとっては追い風です。メインでもマナがかからない墓地対策カードが1枚あるので全投入すると合わせて4枚、期待値的には引ける数字です。墓地を空にして、相手のライフも空にしてあげましょう。
《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
追加のハンデスカードです。除去カードで対象に取れないクリーチャーやコンボの決め手、全体除去やアーティファクト、エンチャント等を指定しましょう。1ゲーム目で自分にとって驚異である何枚かのカードを見てると思いますが、その中でも「撃たれたら負ける」カードを指定して下さい。2ゲーム目以降は相手もサイドボーディングを行っているので、フラッシュバックも含めて積極的に使って行きましょう。
《真髄の針/Pithing Needle》
このデッキにはアーティファクトやエンチャントに対抗するカードがハンデスくらいしかありません。なので、起動型能力を持つ「置物(エンチャントやアーティファクトの通称。)」をケアしきれなかった場合に於いては、このカードが有効に働く場面も多いと思います。しかし、このカードが効力を発揮するのは起動型能力を封じる事のみで、常在型能力のアーティファクトやエンチャントには全く効果がありません。そんな時は…やっぱりハンデスに頼るしかなさそうですね。対策を取られる前にスピード勝負に持ち込み、短期決戦でケリをつけましょう。
《根絶/Extirpate》
このカードは対コンボに特化したカードだと思われがちですが、そんな事はありません。実は全体除去を《根絶/Extirpate》するのも、かなり有効な手段と成り得るのです。特に撹乱的アグロはカウンターを中心に「クリーチャー」を守る事が多いです。クリーチャーに対して干渉してこないハンデスは打ち消されないこともままある為、ハンデスが通った後にこのカードで蓋をする、といった作戦が比較的容易に行えます。相手の技量と自分のプレイング次第と言えばそれまでですが、狙う価値のある戦略だと思っています。
《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
対スペルデッキ対策のカードです。アグロデッキに対してはほとんど意味を成さないので呼ばれる事は稀ですが、スペルを中心に組み上げているデッキには劇的に刺さります。相手からのスペルでの干渉を若干でも抑える事が出来たならば、その稼ぎ出した数ターンで勝利をもぎ取る事を可能にします。カウンターカードやロックカードのほとんどは非クリーチャースペルである事が多いので、そういったタイプのデッキにも有効に働きます。ゲーム序盤に最も効力を発揮するカードなので、出来る事なら初期手札に欲しい1枚です。
《残響する衰微/Echoing Decay》
同系統デッキに対する解答として採用してあるカードです。このデッキにも言えることですが、ウィニー型のアグロデッキは同じクリーチャーを複数枚搭載していることが非常に多いです。そして、ウィニークリーチャーのほとんどが2/2までのサイズなので、一方的なアドバンテージを獲得する事が出来ます。また、トークンカードでボードアドバンテージを稼いでくる様なデッキに対しても解答と成り得ます。単純にクリーチャーの数で勝負を持ち込む場合に採用してあげてください。
【有効なサイドボーディング例】
◆ vsアグロデッキ
OUT
1 《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
2 《強迫/Duress》
2 《冬の宝珠/Winter Orb》
IN
3 《根絶/Extirpate》
2 《残響する衰微/Echoing Decay》
▼《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》は黒のトリプルシンボルです。アグロ対アグロの場合、どうしても速度勝負になりがちなので、3マナというやや重いこのカードは速度の足枷になってしまう事がありがちです。アグロは除去やバーンカードとクリーチャーの数を比べると、クリーチャーの方が少ない事の方が稀です。《強迫/Duress》は相手の「土地でもクリーチャーでもないカード」を落とすので、ミスをする可能性が高いのです。《冬の宝珠/Winter Orb》の仕事は「動きを妨害する動きを防ぐ」のが基本となっており、アグロデッキの様なマナ・カーブが低いデッキに対しては、あまり有効に機能しない事の方が多いです。《根絶/Extirpate》はメインクロッカーや除去を根こそぎ奪い取る事に優れています。手札にメインクロッカーが潜んでいることも多いので、1枚でもクロッカーが落ちたら使って行きましょう。相手のクリーチャーの絶対数が減れば、数で勝負に出ても勝つ事が出来ます。また、《根絶/Extirpate》は相手のドロー後に使用するのが基本原則です。《残響する衰微/Echoing Decay》は個別の説明でもした通り、ウィニーに対して劇的に刺さります。同名のクリーチャーが場に2体以上相手の場に出ているのを見て、最も有効な場面で撃ちましょう。
◆ vsミッドレンジデッキ
OUT
1 《カーノファージ/Carnophage》
2 《血の署名/Sign in Blood》
2 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
3 《根絶/Extirpate》
▼《カーノファージ/Carnophage》はミッドレンジデッキに搭載されているクリーチャー達と比べると、どうしても力不足になりがちです。アップキープにダメージを受けるだけの存在となってしまう事が多いでしょう。《血の署名/Sign in Blood》はテンポを崩す可能性が多いにありえるカードです。ただでさえボードアドバンテージを重ねてくるミッドレンジに対して、自らテンポを崩すような事は決して行ってはならないのです。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》は単なるドローカードに成り下がりがちです。なぜならばミッドレンジデッキに対してウィニークリーチャーを残しておく事は、除去カードやクリーチャーの質の関係上、非常に難しいからです。ドローの役割は《血の公証人/Blood Scrivener》に任せる事にしましょう。戦略的には、全体除去やこのデッキの苦手とする除去の効かない中型クリーチャー等を《陰謀団式療法/Cabal Therapy》で落とし、更にデッキ内から《根絶/Extirpate》する事を目標とします。システムクリーチャーは《悲劇的な過ち/Tragic Slip》で潰し、残ったクロッカーは《四肢切断/Dismember》していきましょう。クリーチャーのサイズで差が付くことが多いですが、《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》や育った《屍肉喰らい/Carrion Feeder》、《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》から出てくるトークンは、ミッドレンジのクリーチャー達に太刀打ち出来る可能性を秘めたクリーチャーです。意識して使っていきましょう。
◆ vsランプデッキ
OUT
2 《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
▼ランプデッキの根底にあるものは、コンボデッキのそれと同様な動きです。ハンデスでランプカードを引き抜き、相手がもたもたしている内に勝負を決めるのがなかなか良い攻め方なのではないでしょうか。それには初手でキープするハンドがとても重要になってきます。少なくとも1枚以上ハンデスがある手札をキープする様に心掛けて下さい。ランプデッキの最も恐ろしい脅威は、どれもかなりのマナ数を要求してきます。その脅威を序盤からのマナ加速によって1ターンでも早く場に着地させようとするのがランプデッキたる所以なので、コチラの《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》が出る頃には、相手の場に太刀打ち出来ない程の巨大クリーチャーが着地していると思われるので、控えに下がってもらう事にしましょう。ランプデッキのもう一つの特徴として、変形型で無い限りは「直接手札から脅威を唱える」事がほとんどです。つまり、相手が勝負を決めに来る際は必ずと言っていい程、手札にその脅威が存在しているのです。と、言う事は…そう、《陰謀団式療法/Cabal Therapy》でカードを指定して墓地に沈める事が可能なのです。また、相手のランプカードや脅威を根こそぎ《根絶/Extirpate》してしまうのも時には有効な作戦となるでしょう。
◆ vsコントロールデッキ
OUT
2 《血の署名/Sign in Blood》
1 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
4 《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
IN
3 《根絶/Extirpate》
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
2 《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
▼コントロールデッキは、コチラのボードアドバンテージを相対的に塞ぎ込もうとしてきます。なので基本的に相手には「自分で選んで対処をしている」と思わせる事が大事です。そう考えると《血の署名/Sign in Blood》に対して相手が対処してくれるかと言ったら…答えはNoとなるでしょう。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》も同様の理由から抜ける事になります。相手にとっては1枚のドローより、場に脅威を出される方が嫌と感じることでしょう。それに、これは起動型能力なのでその事も手伝い、ほぼ確実にスルーされてしまう事が多いです。《悲劇的な過ち/Tragic Slip》は、コントロールデッキの大半がウィニークリーチャーを搭載していない事が多いので、交換するカードの筆頭として挙げられます。《根絶/Extirpate》の強みの内の一つに、「ほぼカウンターされない」と言った事が挙げられる事と思います。つまりこのカードは、撃った時点でほぼ確実に効果を発揮するという事です。このカードを最も有効に使うのであれば、上手く《陰謀団式療法/Cabal Therapy》を通す事から始めましょう。幸い《陰謀団式療法/Cabal Therapy》のフラッシュバックコストはマナを使用しないので、相手のタップアウトの隙をつけば、これもまたほぼ確実に通す事が出来るでしょう。その後、デッキの中に少数組み込まれているであろうフィニッシャーを全て追放領域に送り込み、相手の脅威を完全にシャットダウンさせる事が出来たのであれば、もう勝利は目前です。《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》はカウンターカードや場をコントロールする呪文を遅らせる事が出来ます。相手がもたもたしている間にゾンビの群れを突っ込ませましょう。
◆ vsコンボデッキ
OUT
4 《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
1 《屍肉喰らい/Carrion Feeder》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
3 《根絶/Extirpate》
▼コントロールと同じでデッキの種類にもよりますが、コンボデッキはデッキに搭載されているクリーチャー数が少ない事が多いです。なので、《悲劇的な過ち/Tragic Slip》は撃つ対象があまりおらず、手札の中で眠ったままになりがちです。《屍肉喰らい/Carrion Feeder》に関しては、きっとこの子を育てている時間がないと思われるからです。おそらく《屍肉喰らい/Carrion Feeder》が5/5の程良いサイズになる頃には、コチラのライフやライブラリーはとっくに空にされている事でしょう。コンボデッキもアグロデッキとは違ったベクトルで「速度」を追い求めているデッキと言っても差し支えないので、そのような事が起こります。コンボデッキと戦う為にはまず、相手がどのような種類のコンボデッキなのかをしっかり見抜く必要があります。コンボデッキは特定のカードの組み合わせが非常に強力なのですが、逆を言えばその組み合わせさえ崩してしまえば、そこまで恐れるものは無くなるのです。キーカードはデッキによって違ってくるでしょうが、そのどちらか一方を《強迫/Duress》や《陰謀団式療法/Cabal Therapy》で落とした上で《根絶/Extirpate》してしまえば、かなり戦いやすくなる事は間違いないです。しかし、コンボデッキによっては勝負を決めてくるパターンが数種類ある物も存在するので、油断は禁物です。また、呪文を連鎖してくる、例えば「ドラゴンストーム」の様なデッキには《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》が有効です。覚えておいて損は無いでしょう。
◆ vs撹乱的アグロデッキ
OUT
2 《血の署名/Sign in Blood》
2 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
IN
2 《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
▼撹乱的アグロデッキはデッキの構成上、どのようなデッキにも対応できる様に構築されていることが多いです。汎用的な反面、それを言い換えるのであれば「器用貧乏」になりがちだということです。その攻守を打ち崩すのには1つの「風穴」を開けれやれば、必然的に答えは見えてくるのです。《血の署名/Sign in Blood》はドロー加速にしかならず、相手が脅威と感じてくれることは少ないでしょう。つまり、「ドローで引いてきたカードを対処すればいいのだ」と。故にこのカードは「自らに2点ダメージを負う」とだけ書かれたカードになってしまいます。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》の能力は打ち消されにくく優秀ですが、どんなデッキにも対処できるように作られていることが多い関係上、起動型能力を打ち消す呪文も含まれていることがほとんどです。クリーチャーを並べながらこの能力を連打するまでには時間が掛かり、これも決定打となる場面が少なくなってしまいます。どちらかと言うと「コチラのやりたい事をさせない」動きが強いデッキである撹乱的アグロは、その中心が呪文であることが多いです。なので《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》を刺しつつ動きを緩慢にし、相手の勝ち手段は《陰謀団式療法/Cabal Therapy》等で落として行くのがベターです。その小さく空いた「風穴」に、コチラの中型クリーチャーを突撃させれば、その風穴はみるみる広がっていく事でしょう。
◆その他
《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt》と《真髄の針/Pithing Needle》に関しては、相手が使ってくるカードに応じて投入して下さい。投入した際、この2枚のカードはほぼ確実に初期手札に欲しいカードとなっていますので、残り手札1枚になるまでマリガンをするくらいの気持ちを心掛けてください。また、このデッキの最大の弱点は、早いターンに《虚空の杯/Chalice of the Void》を置かれたら、勝ち手段は皆無な事です。勝算はゼロ以外の何物でもないので、素直に負けを認めましょう。それがどうしても嫌なのであれば、サイドボードに《Gate to Phyrexia》を忍ばせるといった事も考えられます。例えそのプランを採用したとしても勝てる確率はほぼゼロに等しいので、あまりお勧めはしません。
【ゾンビ達の基本的な飼育方法。】
・基本的にこのデッキは土地が1枚あれば回ります。土地が1枚、クリーチャーが2枚、除去かハンデスが1枚あれば、好スタートをきれるでしょう。
・このデッキの最も基本的なプランは、先にも記しましたが「2点ダメージを相手本体に10回叩き込む」となっています。2/2クリーチャーを中心に組まれたこのデッキの理想としては、1ターン目からクリーチャーを展開し、対戦相手にプレッシャーを掛けていけるのが望ましいですね。場に3〜4体のゾンビが蠢いているなら、なかなか立派なゾンビマスターと言えるでしょう。準備が整ったら攻撃、攻撃、更に攻撃です!手を休めることの無い様、怒涛のラッシュをブチかましてください!
・時にはブロックされ、儚く散って行く事を知りつつもアタックすべき状況があることを忘れないで下さい。3体でアタックして1匹しかブロックされなければ4点ダメージです。一刻も早く勝負を決め、相手の体制が整う前に決着をつけるのがアグロデッキのセオリーです。
・このデッキには除去呪文が合計で8枚搭載されていますが、ゲーム中に引けるとすればおおよそ2枚程度でしょう。その除去カードを無駄にしないように使っていって下さい。このデッキの戦略は「数で押す」です。2/2以下のクリーチャーは同士討ち出来ると思うので、コチラの戦略を崩してくるようなシステムクリーチャーや、3/3以上のクロッカーの為に除去を使って行きましょう。
・ハンデスカードはとても貴重な存在です。対戦相手が呪文を唱えて場に出る、効果を発揮する前に、手札にある状態でそのカードを叩き落とす事が出来るならば、あなたへの被害はゼロです。重ね重ねになりますが、全体除去や除去の効かない大型クリーチャー、攻撃制限カードはこのデッキに大きな致命傷を負わせる事になるので、そういったカードを事前にノックアウトする事こそがゾンビマスター、言うなれば黒遣いとしての嗜みと言えるでしょう。
・サイドボーディングの際は、搭載されているクリーチャー枚数に気を付けて下さい。このデッキはほぼ確実にビートダウンで片を付けるデッキなので、ある程度のクリーチャー数が絶対必要になってきます。安易にクリーチャーを抜く事は避けたいですね。スピードを意識しつつ、場に出にくい《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》や《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》のトークンと相談しながらサイドボーディングを行ない、デッキを再構築させてください。
上手にゾンビ達を使役し、立派なゾンビマスターになってくださいね。
文章:Ebth Mousound
翻訳:ヱロゐ人。
【脳味噌が食べられてしまう前に。】
みなさんは「ゾンビ」と聞くと何を思い浮かべますか?ある人は『倒しても倒しても何度も蘇る』と言うでしょう。またある人は『群れで襲いかかってくる』とも。少ない意見で言えば『死体が合体して、1つの巨大なゾンビになるんだ!』なんてのもあったりします。
よろしい、全て叶えましょう!このデッキにはその全ての要素が入っています。ゾンビ達は倒されても倒されても墓地や手札から何度も蘇り、対戦相手に群れで襲いかかります。そして死体が「補充」された暁には、巨大なゾンビの王が戦場に降臨するのです!
このデッキはそういった「フレイバー」を重視して作られていますが、実力は相当なモノです。自信を持ってオススメ出来るデッキに仕上がっています。このデッキを使った貴方はその強さと、醜くも美しい耽美なるゾンビの世界に魅了されてしまう事でしょう。
また、このデッキの名前はインスピレーションを受けた同名のボードゲームから付けさせてもらいました。単純なルールで皆で盛り上がる事の出来る、素晴らしい「バカゲー(賞賛の言葉です)」になっているので、機会があったら是非プレイしてみて下さい。
…おや?そうこうしている間にも向こうからやって来てくれたみたいですよ。聞こえてきたでしょう、彼らの呻き声が。ほら、貴方の後ろにも…!
【デッキリスト】
《ゾンビーズ!!! / Zombies!!!》
メインボード / Mainboards
土地 / Lands:17枚
14 《沼/Swamp》
2 《邪悪な岩屋/Unholy Grotto》
1 《ボジューカの沼/Bojuka Bog》
クリーチャー / Creatures:25枚
2 《カーノファージ/Carnophage》
4 《戦墓のグール/Diregraf Ghoul》
2 《肉占い/Sarcomancy》
4 《墓所這い/Gravecrawler》
4 《屍肉喰らい/Carrion Feeder》
3 《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》
2 《血の公証人/Blood Scrivener》
4 《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
呪文 / Spells:18枚
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
2 《強迫/Duress》
4 《四肢切断/Dismember》
4 《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
2 《血の署名/Sign in Blood》
2 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
2 《冬の宝珠/Winter Orb》
サイドボード / Sideboards:15枚
3 《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt》
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
3 《真髄の針/Pithing Needle》
3 《根絶/Extirpate》
2 《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
【各カードの解説】
◆ 土地 / Lands
《沼/Swamp》
このデッキの(仕事をする上での)平均マナコストは何と「1.37」です。その事実がこの土地の少なさを裏付けています。土地の採用枚数が合計で17枚と言うのは、通常のアグロデッキと比べても少ない枚数ですが、その中でも安定してマナを出せる基本地形が14枚しかないと言う事は、逆を言えばそれ以外のカードはマナを発生させる以外の「何らかの仕事」を行うと言う事です。時に十分な枚数の土地を引けない事があるかもしれませんが、このデッキは基本的に土地が1枚あればデッキが動くように作られています。少ないマナを有効活用し、活路を見出してください。
《邪悪な岩屋/Unholy Grotto》
墓地にあるゾンビをライブラリートップに戻すカードです。主にシナジーを形成するのは《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》ですが、その他のカードとも相性は良好です。しかしながら、この土地カードからは無色のマナしか生成する事が出来ないので、土地として換算するには少し不安が残ります。と、言うのも、このデッキに採用しているほとんどのカードは無色のマナを必要としないからです。初手でこの土地をキープする場合には気をつけてください。
《ボジューカの沼/Bojuka Bog》
メインボードから気軽に採用出来る墓地対策カードです。タップインなのでテンポロスになってしまいますが、2枚目以降の「沼」とみるならば、なかなかにいい働きだと思います。対戦相手を対象に取る事が出来なかった場合には自分の墓地を対象に取らざるを得ないので、出すタイミングには気をつけてください。
◆ クリーチャー / Creatures
《カーノファージ/Carnophage》
メインアタッカーです。安定した使役には多少の痛みが伴いますが、それを感じさせない程パワフルな働きをしてくれるでしょう。このクリーチャーもそうですが、このデッキは「2点ダメージを相手本体に10回叩き込む」というプランで成り立っています。1体1体の役割を冷静に見極め、生贄に捧げるかブロッカーにするか、はたまたアタッカーにするのかを的確に指示してあげていって下さい。(何と言っても、この子達には「脳味噌」が無いですからね。)
《戦墓のグール/Diregraf Ghoul》
コチラもこのデッキを代表するメインアタッカーです。一度戦場に出てしまえば《カーノファージ/Carnophage》よりも優秀なので、採用枚数は4枚となっています。タップインが少し煩わしいですが、このデメリットが敗因に繋がることは稀でしょう。また、このデッキのウィニークリーチャー達は全て「使い捨て」と考えて下さい。土地の項目にも少し書きましたが、このデッキは土地の枚数が極端に少なく構成されています。ドローしてくるカードのほとんどは盤面に有効に働くカード達なので、上手に使って試合を有利に進めていって下さい。
《肉占い/Sarcomancy》
コレ自体はエンチャントですが、真の所、このカードは優秀な「ウィニークリーチャー」です。このデッキに関して言えば、デメリットはほぼ感じられないでしょう。1ターン目から2/2クリーチャーを着地させる事が出来るデッキは、そう多くはありません。ゲーム序盤から相手のライフを果敢に攻め、常にライフに於いて優位に立てている様な展開が望ましいですね。
《墓所這い/Gravecrawler》
このデッキのメインエンジンになります。墓地から蘇る事によって《肉占い/Sarcomancy》のデメリットを帳消しにしたり、《陰謀団式療法/Cabal Therapy》のフラッシュバックコストに充てたり、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》に自身を食べさせて彼を成長させたりと、使い方に関しては枚数に暇が無いです。ただしブロックに回る事は出来ないので、相手に対処出来ない程のファッティが出て来た場合は、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》の餌となり、彼を育てる「餌」として尽力して下さい。
《屍肉喰らい/Carrion Feeder》
このデッキのメインエンジンその2です。陰鬱の達成や探索カウンターを乗せる等、この子の行える仕事は多岐に渡ります。また、この子はデッキに入っているクリーチャーの中でも一番の成長株で、上手く育て上げることが出来ればそのサイズは、かのエムラクールすら超えることが出来ることでしょう。カジュアル・クラシックに限った事では無いですが、この子を中心に動く事が出来れば、相手の《剣を鍬に/Swords to Plowshares》や《流刑への道/Path to Exile》をかわす事が容易になります。タイミングを見極めて上手に避けましょう。
《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》
死体を寄せ集める事によって降臨するゾンビの王様です。単体のサイズで見れば、このデッキの中で最大のサイズを持ったクリーチャーです。クリーチャー同士の戦闘に於いて、5/5という巨大なサイズのクリーチャーが落とされる事はまず無いと言っても過言では無いでしょう。バウンス呪文や明滅呪文に弱いという欠点はありますが、それを差し引いたとしても有り余るスピードと火力が対戦相手を恐怖のドン底に叩き落とすでしょう。何せこの王様が着地するのには1マナしか必要としないのですから。
《血の公証人/Blood Scrivener》
このデッキはしばしば手札が無い事に悩まされます。それを逆手に取り、アドバンテージに変えてしまうのがこの子の仕事です。レガシープレイヤーには痛くない《闇の腹心/Dark Confidant》と言えば理解が早いかと思います。この子が無事に着地出来たとしたら、圧倒的なドロー加速と驚異の展開力で、場をゾンビの群れで満たしてあげましょう。腐っても(とは言いつつも、元々身体は腐ってはいますが)サイズは2/1、しっかりとクロックも刻める憎いヤツです。
《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
この子はとにかく仕事が出来る子です。場に出て仕事をして、一度墓地に落ちて仕事をして、場に戻って来て仕事をして、クロックを刻んで仕事をして、また墓地に行って仕事をして…。日本人も尻尾を巻いて逃げ出す程のハードワーカーです。柔軟性に富んだユーティリティカードだと言う事に間違いは無いのですが、黒マナを3つも使う為、少し場に出にくく感じるのが残念な所です。しかし、一度場に出てさえしまえば必要最低限の仕事はこなしているので、出せる場面では積極的に狙って行きましょう。
◆ 呪文 / Spells
《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
相手のカードを狙い撃ちして落とせるスナイパーカードです。使いこなす為には相当量の知識が伴いますが、2ゲーム目以降であれば比較的容易に狙い落とせるでしょう。基本的には《神の怒り/Wrath of God》の様な全体除去を叩き落とす為に使いますが、黒という色の特性上アーティファクトとエンチャントに触りにくい為、それらのカードを落とすのにも使えます。クリーチャーが墓地に落ちる事をトリガーとするカードが場に出ている場合は、即座にフラッシュバックを使用し、2回続けて撃って行きましょう。カードを2枚使用してしまいますが、相手の手札で最も撃たれたくないカードを確実に落とせます。
《強迫/Duress》
覚えておいて欲しいのが、このデッキは比較的多めにクリーチャー除去が搭載されていますが、クリーチャー以外のカードに積極的干渉が出来るのは、ハンデスカードを除くと《冬の宝珠/Winter Orb》だけということです。クリーチャー以外の呪文は、撃たれる前に墓地に送ってあげましょう。ゲーム序盤に撃てればほぼ間違い無く何かしらのカードが落せると思います。そして、何と言っても「相手の手札が見えている状況」というのは潜在的アドバンテージを内包しており、カードを使用する順番や除去の使い道など、コチラの戦略を遂行する上でかなり有効に働く事が多いです。また、相手のカウンター呪文を誘えたりもするので、ゲーム中盤から後半に引いてきても腐りにくいカードと言えるでしょう。
《四肢切断/Dismember》
スーサイド要素の強い、低コストの除去カードです。-5/-5に耐えうるクリーチャーはまずいないでしょう。ライフ4点の損失はかなり手痛いですが、構えておくマナが1マナで良いと言うのは、テンポの面から見ても大変優れているカードと言えます。基本的に1マナで撃つ事になるカードなので、残りライフには常に気を付けていて下さい。相手のメインクロッカーを落としつつ、コチラのクリーチャーを通す為に使うので、基本的にはミッドレンジ(目安として3/3)以上のクリーチャーに使うように心掛けていってください。
《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
陰鬱を達成すると落とせないカードはほとんど無くなる、優秀な除去呪文です。基本的には相手のシステムクリーチャーを排除する為に使いますが、《屍肉喰らい/Carrion Feeder》との相性は抜群で、自分の好きなタイミングで陰鬱を達成させ、フィニッシャー級の重量クリーチャーをも落とす事が可能になります。コチラも1マナ構えていればいつでも撃てるので、《四肢切断/Dismember》と合わせてブラフが機能します。時には自殺覚悟のチャンプアタックをしてみても面白いかもしれませんね。
《血の署名/Sign in Blood》
残り2点を削り取る、フィニッシャーにもなり得るドローカードです。自分の手札が少ない場合にはドローソースとして機能し、相手のライフが少ない場合にはダメージソースとして機能します。このカードの実力はかなりのもので、本来ならば4枚搭載したい所です。しかしながらこのカード唯一の弱点として「テンポロス」が挙げられます。この唯一の弱点が、速さが重要視されるアグロデッキにとっては何とも致命的で、マナを切り詰めているこのデッキにとっては更に明確な弱点となってしまいます。言い過ぎかもしれませんが、「1ターンを無駄にしてカードを2枚得る」と言っても差し支えないと思っています。アグロデッキの1ターンは何物にも代え難いもので、テンポを崩してまでカードが欲しい事は稀です。それに、このデッキには他にもドローソースが存在しているので、このカードが輝ける場面はそこまで多くはありません。なので、この枚数に落ち着きました。アーキタイプによって搭載枚数に差が出る良い例ですね。
《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
ドローをしながら相手のライフを攻められる一人二役のカードです。マナコストを見てもらえば分かる通り、このカードが場に出る事はまずありえません。サイクリング能力を目当てに使っていきます。なので「呪文」の項目に当て込みました。ドローをしながら(平均的に)2点のライフロスを狙えるのは強い動きだと思います。また、場に《邪悪な岩屋/Unholy Grotto》が出ていれば、無限回収も出来ます。インスタントタイミングで使用可能かつ打ち消されにくいので、状況を見極めて使ってあげてください。
《冬の宝珠/Winter Orb》
このデッキの中では少し異色に映るかもしれませんが、このカードはこのデッキにピタリと当てはまります。基本的に1マナで動けるデッキなので、アンタップ制限が他のデッキと比べて苦にならない事が多いのです。そして、このデッキが苦手とする「ミッドレンジ」は、全体除去を搭載している傾向が強いです。もしも全体除去を撃たれたとしても、このカードが場に出ていれば、リカバリーまでの時間を稼ぎ出してくれる事でしょう。過去に存在した強力なアーティファクトの力を存分に味わって下さい。
◆ サイドボード / Sideboards
サイドボードの概念は別項目で解説するので、ここでは採用傾向を簡単にお伝えします。説明しなくても既にご存知だとは思いますが、このデッキのアーキタイプは「アグロ」です。一般的にこのアーキタイプは「コントロール」や「撹乱的アグロ」に強く、「ミッドレンジ」や「コンボ」に弱いです。なので、その部分を補える様にカードを選びました。しかし、一概にはそうとは言えませんので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。また、カジュアル・クラシックではレガシーやモダンと違い、文字通り「無数」のデッキタイプが存在しています。なので必然的にサイドボードは「丸く」なります。その点も併せてご覧ください。
《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt》
何はともあれ墓地対策です。短期決戦型のこのデッキでは、1回でも相手の墓地を空にする事が出来れば、その隙を突き、勝利を掴み取ることができるでしょう。マナが全くかからない事もこのデッキにとっては追い風です。メインでもマナがかからない墓地対策カードが1枚あるので全投入すると合わせて4枚、期待値的には引ける数字です。墓地を空にして、相手のライフも空にしてあげましょう。
《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
追加のハンデスカードです。除去カードで対象に取れないクリーチャーやコンボの決め手、全体除去やアーティファクト、エンチャント等を指定しましょう。1ゲーム目で自分にとって驚異である何枚かのカードを見てると思いますが、その中でも「撃たれたら負ける」カードを指定して下さい。2ゲーム目以降は相手もサイドボーディングを行っているので、フラッシュバックも含めて積極的に使って行きましょう。
《真髄の針/Pithing Needle》
このデッキにはアーティファクトやエンチャントに対抗するカードがハンデスくらいしかありません。なので、起動型能力を持つ「置物(エンチャントやアーティファクトの通称。)」をケアしきれなかった場合に於いては、このカードが有効に働く場面も多いと思います。しかし、このカードが効力を発揮するのは起動型能力を封じる事のみで、常在型能力のアーティファクトやエンチャントには全く効果がありません。そんな時は…やっぱりハンデスに頼るしかなさそうですね。対策を取られる前にスピード勝負に持ち込み、短期決戦でケリをつけましょう。
《根絶/Extirpate》
このカードは対コンボに特化したカードだと思われがちですが、そんな事はありません。実は全体除去を《根絶/Extirpate》するのも、かなり有効な手段と成り得るのです。特に撹乱的アグロはカウンターを中心に「クリーチャー」を守る事が多いです。クリーチャーに対して干渉してこないハンデスは打ち消されないこともままある為、ハンデスが通った後にこのカードで蓋をする、といった作戦が比較的容易に行えます。相手の技量と自分のプレイング次第と言えばそれまでですが、狙う価値のある戦略だと思っています。
《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
対スペルデッキ対策のカードです。アグロデッキに対してはほとんど意味を成さないので呼ばれる事は稀ですが、スペルを中心に組み上げているデッキには劇的に刺さります。相手からのスペルでの干渉を若干でも抑える事が出来たならば、その稼ぎ出した数ターンで勝利をもぎ取る事を可能にします。カウンターカードやロックカードのほとんどは非クリーチャースペルである事が多いので、そういったタイプのデッキにも有効に働きます。ゲーム序盤に最も効力を発揮するカードなので、出来る事なら初期手札に欲しい1枚です。
《残響する衰微/Echoing Decay》
同系統デッキに対する解答として採用してあるカードです。このデッキにも言えることですが、ウィニー型のアグロデッキは同じクリーチャーを複数枚搭載していることが非常に多いです。そして、ウィニークリーチャーのほとんどが2/2までのサイズなので、一方的なアドバンテージを獲得する事が出来ます。また、トークンカードでボードアドバンテージを稼いでくる様なデッキに対しても解答と成り得ます。単純にクリーチャーの数で勝負を持ち込む場合に採用してあげてください。
【有効なサイドボーディング例】
◆ vsアグロデッキ
OUT
1 《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
2 《強迫/Duress》
2 《冬の宝珠/Winter Orb》
IN
3 《根絶/Extirpate》
2 《残響する衰微/Echoing Decay》
▼《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》は黒のトリプルシンボルです。アグロ対アグロの場合、どうしても速度勝負になりがちなので、3マナというやや重いこのカードは速度の足枷になってしまう事がありがちです。アグロは除去やバーンカードとクリーチャーの数を比べると、クリーチャーの方が少ない事の方が稀です。《強迫/Duress》は相手の「土地でもクリーチャーでもないカード」を落とすので、ミスをする可能性が高いのです。《冬の宝珠/Winter Orb》の仕事は「動きを妨害する動きを防ぐ」のが基本となっており、アグロデッキの様なマナ・カーブが低いデッキに対しては、あまり有効に機能しない事の方が多いです。《根絶/Extirpate》はメインクロッカーや除去を根こそぎ奪い取る事に優れています。手札にメインクロッカーが潜んでいることも多いので、1枚でもクロッカーが落ちたら使って行きましょう。相手のクリーチャーの絶対数が減れば、数で勝負に出ても勝つ事が出来ます。また、《根絶/Extirpate》は相手のドロー後に使用するのが基本原則です。《残響する衰微/Echoing Decay》は個別の説明でもした通り、ウィニーに対して劇的に刺さります。同名のクリーチャーが場に2体以上相手の場に出ているのを見て、最も有効な場面で撃ちましょう。
◆ vsミッドレンジデッキ
OUT
1 《カーノファージ/Carnophage》
2 《血の署名/Sign in Blood》
2 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
3 《根絶/Extirpate》
▼《カーノファージ/Carnophage》はミッドレンジデッキに搭載されているクリーチャー達と比べると、どうしても力不足になりがちです。アップキープにダメージを受けるだけの存在となってしまう事が多いでしょう。《血の署名/Sign in Blood》はテンポを崩す可能性が多いにありえるカードです。ただでさえボードアドバンテージを重ねてくるミッドレンジに対して、自らテンポを崩すような事は決して行ってはならないのです。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》は単なるドローカードに成り下がりがちです。なぜならばミッドレンジデッキに対してウィニークリーチャーを残しておく事は、除去カードやクリーチャーの質の関係上、非常に難しいからです。ドローの役割は《血の公証人/Blood Scrivener》に任せる事にしましょう。戦略的には、全体除去やこのデッキの苦手とする除去の効かない中型クリーチャー等を《陰謀団式療法/Cabal Therapy》で落とし、更にデッキ内から《根絶/Extirpate》する事を目標とします。システムクリーチャーは《悲劇的な過ち/Tragic Slip》で潰し、残ったクロッカーは《四肢切断/Dismember》していきましょう。クリーチャーのサイズで差が付くことが多いですが、《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》や育った《屍肉喰らい/Carrion Feeder》、《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》から出てくるトークンは、ミッドレンジのクリーチャー達に太刀打ち出来る可能性を秘めたクリーチャーです。意識して使っていきましょう。
◆ vsランプデッキ
OUT
2 《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
▼ランプデッキの根底にあるものは、コンボデッキのそれと同様な動きです。ハンデスでランプカードを引き抜き、相手がもたもたしている内に勝負を決めるのがなかなか良い攻め方なのではないでしょうか。それには初手でキープするハンドがとても重要になってきます。少なくとも1枚以上ハンデスがある手札をキープする様に心掛けて下さい。ランプデッキの最も恐ろしい脅威は、どれもかなりのマナ数を要求してきます。その脅威を序盤からのマナ加速によって1ターンでも早く場に着地させようとするのがランプデッキたる所以なので、コチラの《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》が出る頃には、相手の場に太刀打ち出来ない程の巨大クリーチャーが着地していると思われるので、控えに下がってもらう事にしましょう。ランプデッキのもう一つの特徴として、変形型で無い限りは「直接手札から脅威を唱える」事がほとんどです。つまり、相手が勝負を決めに来る際は必ずと言っていい程、手札にその脅威が存在しているのです。と、言う事は…そう、《陰謀団式療法/Cabal Therapy》でカードを指定して墓地に沈める事が可能なのです。また、相手のランプカードや脅威を根こそぎ《根絶/Extirpate》してしまうのも時には有効な作戦となるでしょう。
◆ vsコントロールデッキ
OUT
2 《血の署名/Sign in Blood》
1 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
4 《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
IN
3 《根絶/Extirpate》
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
2 《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
▼コントロールデッキは、コチラのボードアドバンテージを相対的に塞ぎ込もうとしてきます。なので基本的に相手には「自分で選んで対処をしている」と思わせる事が大事です。そう考えると《血の署名/Sign in Blood》に対して相手が対処してくれるかと言ったら…答えはNoとなるでしょう。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》も同様の理由から抜ける事になります。相手にとっては1枚のドローより、場に脅威を出される方が嫌と感じることでしょう。それに、これは起動型能力なのでその事も手伝い、ほぼ確実にスルーされてしまう事が多いです。《悲劇的な過ち/Tragic Slip》は、コントロールデッキの大半がウィニークリーチャーを搭載していない事が多いので、交換するカードの筆頭として挙げられます。《根絶/Extirpate》の強みの内の一つに、「ほぼカウンターされない」と言った事が挙げられる事と思います。つまりこのカードは、撃った時点でほぼ確実に効果を発揮するという事です。このカードを最も有効に使うのであれば、上手く《陰謀団式療法/Cabal Therapy》を通す事から始めましょう。幸い《陰謀団式療法/Cabal Therapy》のフラッシュバックコストはマナを使用しないので、相手のタップアウトの隙をつけば、これもまたほぼ確実に通す事が出来るでしょう。その後、デッキの中に少数組み込まれているであろうフィニッシャーを全て追放領域に送り込み、相手の脅威を完全にシャットダウンさせる事が出来たのであれば、もう勝利は目前です。《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》はカウンターカードや場をコントロールする呪文を遅らせる事が出来ます。相手がもたもたしている間にゾンビの群れを突っ込ませましょう。
◆ vsコンボデッキ
OUT
4 《悲劇的な過ち/Tragic Slip》
1 《屍肉喰らい/Carrion Feeder》
IN
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
3 《根絶/Extirpate》
▼コントロールと同じでデッキの種類にもよりますが、コンボデッキはデッキに搭載されているクリーチャー数が少ない事が多いです。なので、《悲劇的な過ち/Tragic Slip》は撃つ対象があまりおらず、手札の中で眠ったままになりがちです。《屍肉喰らい/Carrion Feeder》に関しては、きっとこの子を育てている時間がないと思われるからです。おそらく《屍肉喰らい/Carrion Feeder》が5/5の程良いサイズになる頃には、コチラのライフやライブラリーはとっくに空にされている事でしょう。コンボデッキもアグロデッキとは違ったベクトルで「速度」を追い求めているデッキと言っても差し支えないので、そのような事が起こります。コンボデッキと戦う為にはまず、相手がどのような種類のコンボデッキなのかをしっかり見抜く必要があります。コンボデッキは特定のカードの組み合わせが非常に強力なのですが、逆を言えばその組み合わせさえ崩してしまえば、そこまで恐れるものは無くなるのです。キーカードはデッキによって違ってくるでしょうが、そのどちらか一方を《強迫/Duress》や《陰謀団式療法/Cabal Therapy》で落とした上で《根絶/Extirpate》してしまえば、かなり戦いやすくなる事は間違いないです。しかし、コンボデッキによっては勝負を決めてくるパターンが数種類ある物も存在するので、油断は禁物です。また、呪文を連鎖してくる、例えば「ドラゴンストーム」の様なデッキには《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》が有効です。覚えておいて損は無いでしょう。
◆ vs撹乱的アグロデッキ
OUT
2 《血の署名/Sign in Blood》
2 《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》
IN
2 《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》
2 《陰謀団式療法/Cabal Therapy》
▼撹乱的アグロデッキはデッキの構成上、どのようなデッキにも対応できる様に構築されていることが多いです。汎用的な反面、それを言い換えるのであれば「器用貧乏」になりがちだということです。その攻守を打ち崩すのには1つの「風穴」を開けれやれば、必然的に答えは見えてくるのです。《血の署名/Sign in Blood》はドロー加速にしかならず、相手が脅威と感じてくれることは少ないでしょう。つまり、「ドローで引いてきたカードを対処すればいいのだ」と。故にこのカードは「自らに2点ダメージを負う」とだけ書かれたカードになってしまいます。《宝石の手の汚染者/Gempalm Polluter》の能力は打ち消されにくく優秀ですが、どんなデッキにも対処できるように作られていることが多い関係上、起動型能力を打ち消す呪文も含まれていることがほとんどです。クリーチャーを並べながらこの能力を連打するまでには時間が掛かり、これも決定打となる場面が少なくなってしまいます。どちらかと言うと「コチラのやりたい事をさせない」動きが強いデッキである撹乱的アグロは、その中心が呪文であることが多いです。なので《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》を刺しつつ動きを緩慢にし、相手の勝ち手段は《陰謀団式療法/Cabal Therapy》等で落として行くのがベターです。その小さく空いた「風穴」に、コチラの中型クリーチャーを突撃させれば、その風穴はみるみる広がっていく事でしょう。
◆その他
《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt》と《真髄の針/Pithing Needle》に関しては、相手が使ってくるカードに応じて投入して下さい。投入した際、この2枚のカードはほぼ確実に初期手札に欲しいカードとなっていますので、残り手札1枚になるまでマリガンをするくらいの気持ちを心掛けてください。また、このデッキの最大の弱点は、早いターンに《虚空の杯/Chalice of the Void》を置かれたら、勝ち手段は皆無な事です。勝算はゼロ以外の何物でもないので、素直に負けを認めましょう。それがどうしても嫌なのであれば、サイドボードに《Gate to Phyrexia》を忍ばせるといった事も考えられます。例えそのプランを採用したとしても勝てる確率はほぼゼロに等しいので、あまりお勧めはしません。
【ゾンビ達の基本的な飼育方法。】
・基本的にこのデッキは土地が1枚あれば回ります。土地が1枚、クリーチャーが2枚、除去かハンデスが1枚あれば、好スタートをきれるでしょう。
・このデッキの最も基本的なプランは、先にも記しましたが「2点ダメージを相手本体に10回叩き込む」となっています。2/2クリーチャーを中心に組まれたこのデッキの理想としては、1ターン目からクリーチャーを展開し、対戦相手にプレッシャーを掛けていけるのが望ましいですね。場に3〜4体のゾンビが蠢いているなら、なかなか立派なゾンビマスターと言えるでしょう。準備が整ったら攻撃、攻撃、更に攻撃です!手を休めることの無い様、怒涛のラッシュをブチかましてください!
・時にはブロックされ、儚く散って行く事を知りつつもアタックすべき状況があることを忘れないで下さい。3体でアタックして1匹しかブロックされなければ4点ダメージです。一刻も早く勝負を決め、相手の体制が整う前に決着をつけるのがアグロデッキのセオリーです。
・このデッキには除去呪文が合計で8枚搭載されていますが、ゲーム中に引けるとすればおおよそ2枚程度でしょう。その除去カードを無駄にしないように使っていって下さい。このデッキの戦略は「数で押す」です。2/2以下のクリーチャーは同士討ち出来ると思うので、コチラの戦略を崩してくるようなシステムクリーチャーや、3/3以上のクロッカーの為に除去を使って行きましょう。
・ハンデスカードはとても貴重な存在です。対戦相手が呪文を唱えて場に出る、効果を発揮する前に、手札にある状態でそのカードを叩き落とす事が出来るならば、あなたへの被害はゼロです。重ね重ねになりますが、全体除去や除去の効かない大型クリーチャー、攻撃制限カードはこのデッキに大きな致命傷を負わせる事になるので、そういったカードを事前にノックアウトする事こそがゾンビマスター、言うなれば黒遣いとしての嗜みと言えるでしょう。
・サイドボーディングの際は、搭載されているクリーチャー枚数に気を付けて下さい。このデッキはほぼ確実にビートダウンで片を付けるデッキなので、ある程度のクリーチャー数が絶対必要になってきます。安易にクリーチャーを抜く事は避けたいですね。スピードを意識しつつ、場に出にくい《ゲラルフの伝書使/Geralf’s Messenger》や《墓所王の探索/Quest for the Gravelord》のトークンと相談しながらサイドボーディングを行ない、デッキを再構築させてください。
上手にゾンビ達を使役し、立派なゾンビマスターになってくださいね。
文章:Ebth Mousound
翻訳:ヱロゐ人。
緑単色デッキの戦略:対戦相手の見極め方。
2012年1月29日 MTG Article コメント (6)
前回…と言っても随分前ですが、緑単色デッキの「セニョールストンピィ」について書きました。
⇒http://nextlevelgreen.diarynote.jp/201109221724386210/
おかげさまで大盛況みたいで、未だに検索をかけてやって来てくれる人達がいるみたいですね。ありがたいことです。まぁ、ハッキリ言ってあそこまで詳しくセニョールストンピィを説明している所なんて無いから当たり前と言えば当たり前ですがね。←
と、言うことで前回は「セニョールストンピィ」に絞って文章アレンジっつー事で書いたので、今回はオリジナルの文章で、緑を遣う(※使う=× 遣う=○)にあたって覚えておいた方がいい事を書きたいと思います。今回のキーワードは「MTG 緑 戦略」と言ったところでしょうか。
ま、書いてある事は緑に限った話では無いと思いますが、こと緑を遣う場合においては他の色以上に重要な事なので書こうと思います。ついでに言うと、IPPANが思っている以上に「緑単色」って言うのは非常に難しいです。だから、下記の様な非常に細かい所まで気を遣わなければ勝ちに繋げられないんですね。僕の場合はさらにパワーカードの使用を控えている事もあり、殊更難しくなっています。
難しいだけで不可能じゃないって言うのがミソ。簡単に勝ちたい方はこの日記からご退場ください。お前向けに書いてないからさ。
あと、どうでもいいけど「緑単色デッキ」って言うのにここまで偏執的、「緑に対して狂信者」な人物は世界中のMTGプレイヤーを探しても僕くらいだそうです。
純潔の緑単色を遣っている中で世界一。ってか世界で唯一。世界で一番ってきもっちー!
…んじゃ、始めますね。
プレイング・デコンストラクション
-プレイングを解体解説する-
「緑単色デッキにおける戦略と対戦相手のレベルの見極め方」
【はじめに】
この文章は純粋な「緑単色デッキ」で対戦相手に勝つという事を念頭に書いたものであって、全ての状況に当てはまる事だと思わないで下さい。また、文章の節々に辛辣な言葉が書かれているので気分を害する可能性があります。そういう文章に嫌悪感を抱く方は読まないでいただける様お願いします。
【カード1枚、されど1枚】
1枚のカードで出来る事は沢山あります。そして、そこから見えてくる事はそのカードが出来る事以上にあるのです。その一つ一つを見落とさずに対戦相手の力量を見誤らなければ、それはそれは非常に強力な「不意打ち(Sucker Punch)」が出来る事でしょう。
それにはまず相手のレベルを見極め、コチラのカードが効果を最大限に発揮できる状況を作り出さなくてはなりません。ここで間違えて欲しくないのが、「最高の状況」というものは自ら作り出すモノ、と言うことです。ゲーム全体を見通し、対戦相手を自分の有利な方へと導いてください。真のボードコントロールとは盤面では無く、ゲーム全体を掌握できる「一つ一つのプレイング」にあると言うことを覚えておいてください。
では、どのように対戦相手のレベルを見極めるのかを、以下の事例を元に紹介します。
=======================================================
【事例1】《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》を使ったコンバット例
=======================================================
1-1:あなたが1マナ以上出る状況で《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》でチャンプアタックをした場合。
(※チャンプアタック=対戦相手がアンタップ状態のクリーチャーをコントロールしている状態で、そのクリーチャーよりサイズが小さいクリーチャーで攻撃すること。 )
本体に通す(アタックをスルーする)プレイヤー=強い。
ブロックするプレイヤー=弱い。
クリーチャーでブロックしてきた場合、あなたの対戦相手は《巨大化/Giant Growth》を警戒していないと考えられます。この場合、《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》がブロックされて死亡した場合、カードアドバンテージロスになってしまいますが、その後の試合をあなたが有利に進められます。と、言うのも、《巨大化/Giant Growth》を警戒していない=対戦相手は弱いプレイヤーなので、最低でも必ず1回は捲くれる場面が来ると言うことです。
そのチャンスを物にする事が出来るのであれば、盤面をひっくり返せる可能性が出てくると言うことです。しかも、たった1マナの「緑のインスタント」で、です。
また、序盤の「特に意味の無いコンバット」の状況で上記のケースになった場合、《巨大化/Giant Growth》に対してカウンター呪文や《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》に対して除去呪文が飛んで来ることが多々あります。そんなプレイヤーを見ていると、「気でも違ってしまったのか!?」と心配したくなります。
たかが《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》如きに除去?「たかが」《巨大化/Giant Growth》ごときにカウンター?大いに結構じゃないですか!盤面の重要局面以外でのカウンターと除去は、ありがたく受けておくべきです。たった1枚の《巨大化/Giant Growth》で、相手の重要な除去呪文やカウンターを誘い出せた事実に手を叩いて喜びましょう。事実、これは後半の試合結果を動かしかねない重要な出来事です。ここで使わせたカウンターや除去が、あなたのデッキに入っている重要なクリーチャー達に向けられる事は無くなったのですから。
そんな除去呪文大好きなプレイヤーには《巨森の蔦/Vines of Vastwood》をお見舞いしてやりましょう。きっとあなたの対戦相手は「テキストを確認させてください」と言ってくることでしょう。そしたらあなたは高らかにこう言ってあげてください。
「あなたの除去は対象不適正で墓地に落ち、僕のクリーチャーは強化されますッ!」ってね。
『つまり、君の対戦相手は後続の脅威の事を何も考えていないお粗末なプレイヤーだって事さ。』
1-2:《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》でブロックする場合。
あなたの場にアンタップ状態の《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》がいる状況で、タフネス1のクリーチャーでアタックしてくるプレイヤー=試合に負ける事を快感だと思えるマゾヒストなプレイヤー。(つまり弱い。)
少しマナがきつい状況でも、手札に森があったら迷わずブロックするのが懸命です。コチラは緑単色デッキ。クリーチャーに触りたくてもなかなか触れないのが現状です。向こうからわざわざアタックしてくるなら対戦相手のクリーチャーの頭数が減らせるので、1対1交換なら喜んでブロックするべきです。
「今」の盤面が辛い状況でもあなたは「クリーチャーの色」の緑。後に展開する厄介で大きなクリーチャーがブロッカーのいなくなった相手を蹂躙することでしょう。
ついでに言うなら、《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》が召喚酔いで無い状況ならば、自らをタップして先述の《巨大化/Giant Growth》を自らを対象に撃つことも可能です。カードを1対1交換した上に「場のアドバンテージ」はあなたが取れるのです。緑にとっては言う事この上無しの状況になります。
『つまり、君の対戦相手はさながら「オズの魔法使い」に出てくるカカシよりも残念なヤツって事さ。』
※また、多くのプレイヤーが「ライフ」と言うリソースを蔑ろに扱いますが、これは大きな間違いです。緑単色のデッキにとって「ライフ1点」とは、対戦相手にしろ自分自身にしろ、何物にも変えがたいものがあります。前半戦でクリーチャーをブロックに回さずに本体のライフを削られ、後半戦で並べたクリーチャーを一掃された事を考えてみて下さい。あなたが着地させたのは5/6のファッティ、相手が着地させたのは3/1のフライヤー。あなたのライフはあと3点で、相手のライフはあと6点。ほら、ライフ1点は大事でしょう?
緑単色デッキにとってクリーチャーとは「クロッカー」であり、「除去呪文」であることをゆめゆめ忘れ得ぬように。なので、場の状況をよく読み、先に繋がるプレイを見通した上で「必要最低限のブロック」をすることを心がけましょう。
======================================================
【事例2】対戦相手の動きからプレイヤーレベルを予測する
======================================================
2-1.対戦相手のフェッチランドの切り方。
対戦相手のドロー後、メインフェイズでフェッチを起動=強い。
あなたのエンドにフェッチを起動=弱い。
基本的にレガシーで使用されているフェッチランドはアンタップインが前提です。ギルドランドでも無ければ、エンドフェイズに切る意味はほとんどありません。あなたのエンドフェイズにインスタント呪文を唱えるならまだしも、あなたのエンドフェイズに何も動かないのにも関わらずフェッチを切るのは「私は先の事を考えていません」と言っているようなものです。
※ドロー後にフェッチランドを切るのであれば、たった今引いてきたカードのマナの色やコストを考慮してから持って来るカードを決められるので、ほんの少しかもしれませんが後の展開に影響する、と言うことです。つまり、細かい所まで気を配っている(隙が少ない)プレイヤーだと言うことです。
そういった「意味の無い所」で、ただ単にフェッチランドを切るようなプレイヤーは警戒心が薄い、想定外の事に弱い、基本的なマニュアル通りの戦い方しかしてこないものです。更に付け加えて言わせてもらうのであれば、あなたの呪文を全く気にしていないとまで言い切れます。
(あなたに知識がある事が前提ですが、)対戦相手の使っているカードでどんなデッキ(アーキタイプ)かが読めることと思います。そういうプレイヤーは大抵オリジナルデッキを遣っていないので、対策も立てやすいです。
そんなフェッチランドをエンドフェイズに切るのが大好きなプレイヤーには《束縛/Bind》をお見舞いしてやりましょう。きっとあなたの対戦相手は「テキストを確認させてください」と言ってくることでしょう。そしたらあなたは高らかにこう言ってあげてください。
「あなたは土地を持って来る事が出来なくなり、僕はカードを1枚ドロー出来ますッ!」ってね。
『つまり、君の対戦相手は上司にペコペコして部下に辛く当たる最低なヤツって事さ。』
※まさかその《束縛/Bind》に対して《Force of Will》を撃ってくるプレイヤーなんてまずいないでしょうが、MTGプレイヤーと言うのは本当に「損をするプレイ」が好きらしく、あながち《Force of Will》が飛んでこないとも言い切れません。
あなたが先手2ターン目で、上記の様な状況でもしも《Force of Will》が飛んできたらありがたくカウンターされるべきでしょう。「まさか土地破壊されるとは思ってなかった」という言い訳は、「緑単色相手にナメたキープするくらいなら、家に帰って彼女のケツでも舐めてろ」と言うセリフと共に、緑単色の《恐怖/Terror》を対戦相手の脳髄に刻み込んであげてください。
2-2.どのランドを持ってくるか
フェッチランドを切ってからランドを着地させるまでの時間が長い=言われるがままに高額請求サイトに会員登録をしてしまう人の良いプレイヤー。(つまり弱い。)
フェッチランドを切ってライブラリーから探している最中に「どの土地を持ってくるか」を悩んでいるプレイヤーも弱いです。
「目的があるためにフェッチを切る」のでは無く、「今、手札にあるカードを使いたいから」という理由だけでフェッチランドを切るのは先のゲームが見えていない証拠で、この上なく弱いです。また、これはフェッチランドだけに限らず、チューター系の呪文を使うときも同義です。「何が欲しいか」と言うことが明確になっていないのにカードをサーチしてくるのは愚の骨頂。だったら他の行動をした方が遥かに有効なハズです。
そういうプレイヤーは総じて「手札だけの勝負」をして来るのが常です。所謂「引きゲー」と言うモノです。「あの時○○が手札にあったら切り抜けられたのに」とか「キープ基準が間違ったかな」とか。そんな言い訳が出てくるという事は、中学生以下の脳味噌だという証明に他なりません。
マジックは基本的に60枚のデッキで構成されているのですから、どんなに頑張ろうとも基本土地カード以外は4/60、つまり1/15までしか1枚のカードを引く確率を上げられません。それが分かっているのですから、金太郎飴みたいに「何処を切っても同じような手札構成になるデッキ」か「一撃必殺の即死コンボデッキ」を使えば良いと言うことです。
そんな言い訳が出てくるようなプレイヤーは、一撃必殺のコンボデッキを使いこなせる技量も資産も無く、コピーデッキを使い、したり顔をして勝ち誇り、たまたま手札に来ていたパワーカードのカードパワーで押し切ったことを「技量」や「デッキ構築」といった言葉で覆い隠そうとするとんでもなく最低なプレイヤーだと僕は思います。
『つまり、君の対戦相手は彼女に隠れてハウツー本を読ん だ上に、彼女とのデートで優柔不断になってしまう甲斐性の無いヤツって事さ。』
【世界一の緑遣いが思うこと】
勝利と言う価値に固執して、デッキ構築や試合そのものを楽しめていない人達が非常に多いように思える昨今。「パワーカード」は過大評価され、「一クセあるカード」 は過小評価されて、淘汰されていきます。
その流れに乗っている人達は、既存のアーキタイプやカード同士のシナジーが全く取れていない所謂「ジャンク」デッキを使って(※使って=○ 遣って=×)いるんですね。僕に言わせてもらえるのであれば、現在のレガシーに存在するデッキの大多数が「ジャンクデッ キ」だと思います。
そんなデッキを使っている(否、「遣われている」)人達は、僕が頼みもしないのに 「デッキ診断」を行って来ます。このカードは弱い?色をタッチした方が強い?そんな事はお前に言われなくても、少なくともお前の1兆2000万倍は心得ている。
そういった人達は僕のデッキの何を知っているんでしょうかね?僕のデッキを回したことが無いのに、どうしてそういった「診断」が出来るのか不思議でなりません。 浅はかな知識だけで僕の崇高な「緑単色」デッキに泥を塗るのは辞めていただきたいですね。
コチラが緑含めた2マナ出せる状況で、対戦相手がコチラのエンドフェイズに手札にカウンターが無いのにも関わらず《渦まく知識/Brainstorm》を唱えるようなものなんですよ。それくらい浅はかです。《種蒔き時/Seedtime》を撃たれたらケアも出来ないクセにでしゃばるのはお門違いってものですね。
だから僕はそんな人達と試合をする気も起きないし、語り合う気も起きない。
…緑を遣うには、これくらい心を尖らせると煽りに負けないし、友達に嫌われるから戦いやすいよ!←
とまぁそんな感じです。また気分が乗ったら書こうと思います。いつになるか分からないですが。
小枝を踏み折れば、骨を折ってあがないとする。
――― ラノワールのエルフの、侵入者への処罰(心の領域的な意味で。)
⇒http://nextlevelgreen.diarynote.jp/201109221724386210/
おかげさまで大盛況みたいで、未だに検索をかけてやって来てくれる人達がいるみたいですね。ありがたいことです。まぁ、ハッキリ言ってあそこまで詳しくセニョールストンピィを説明している所なんて無いから当たり前と言えば当たり前ですがね。←
と、言うことで前回は「セニョールストンピィ」に絞って文章アレンジっつー事で書いたので、今回はオリジナルの文章で、緑を遣う(※使う=× 遣う=○)にあたって覚えておいた方がいい事を書きたいと思います。今回のキーワードは「MTG 緑 戦略」と言ったところでしょうか。
ま、書いてある事は緑に限った話では無いと思いますが、こと緑を遣う場合においては他の色以上に重要な事なので書こうと思います。ついでに言うと、IPPANが思っている以上に「緑単色」って言うのは非常に難しいです。だから、下記の様な非常に細かい所まで気を遣わなければ勝ちに繋げられないんですね。僕の場合はさらにパワーカードの使用を控えている事もあり、殊更難しくなっています。
難しいだけで不可能じゃないって言うのがミソ。簡単に勝ちたい方はこの日記からご退場ください。お前向けに書いてないからさ。
あと、どうでもいいけど「緑単色デッキ」って言うのにここまで偏執的、「緑に対して狂信者」な人物は世界中のMTGプレイヤーを探しても僕くらいだそうです。
純潔の緑単色を遣っている中で世界一。ってか世界で唯一。世界で一番ってきもっちー!
…んじゃ、始めますね。
プレイング・デコンストラクション
-プレイングを解体解説する-
「緑単色デッキにおける戦略と対戦相手のレベルの見極め方」
【はじめに】
この文章は純粋な「緑単色デッキ」で対戦相手に勝つという事を念頭に書いたものであって、全ての状況に当てはまる事だと思わないで下さい。また、文章の節々に辛辣な言葉が書かれているので気分を害する可能性があります。そういう文章に嫌悪感を抱く方は読まないでいただける様お願いします。
【カード1枚、されど1枚】
1枚のカードで出来る事は沢山あります。そして、そこから見えてくる事はそのカードが出来る事以上にあるのです。その一つ一つを見落とさずに対戦相手の力量を見誤らなければ、それはそれは非常に強力な「不意打ち(Sucker Punch)」が出来る事でしょう。
それにはまず相手のレベルを見極め、コチラのカードが効果を最大限に発揮できる状況を作り出さなくてはなりません。ここで間違えて欲しくないのが、「最高の状況」というものは自ら作り出すモノ、と言うことです。ゲーム全体を見通し、対戦相手を自分の有利な方へと導いてください。真のボードコントロールとは盤面では無く、ゲーム全体を掌握できる「一つ一つのプレイング」にあると言うことを覚えておいてください。
では、どのように対戦相手のレベルを見極めるのかを、以下の事例を元に紹介します。
=======================================================
【事例1】《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》を使ったコンバット例
=======================================================
1-1:あなたが1マナ以上出る状況で《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》でチャンプアタックをした場合。
(※チャンプアタック=対戦相手がアンタップ状態のクリーチャーをコントロールしている状態で、そのクリーチャーよりサイズが小さいクリーチャーで攻撃すること。 )
本体に通す(アタックをスルーする)プレイヤー=強い。
ブロックするプレイヤー=弱い。
クリーチャーでブロックしてきた場合、あなたの対戦相手は《巨大化/Giant Growth》を警戒していないと考えられます。この場合、《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》がブロックされて死亡した場合、カードアドバンテージロスになってしまいますが、その後の試合をあなたが有利に進められます。と、言うのも、《巨大化/Giant Growth》を警戒していない=対戦相手は弱いプレイヤーなので、最低でも必ず1回は捲くれる場面が来ると言うことです。
そのチャンスを物にする事が出来るのであれば、盤面をひっくり返せる可能性が出てくると言うことです。しかも、たった1マナの「緑のインスタント」で、です。
また、序盤の「特に意味の無いコンバット」の状況で上記のケースになった場合、《巨大化/Giant Growth》に対してカウンター呪文や《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》に対して除去呪文が飛んで来ることが多々あります。そんなプレイヤーを見ていると、「気でも違ってしまったのか!?」と心配したくなります。
たかが《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》如きに除去?「たかが」《巨大化/Giant Growth》ごときにカウンター?大いに結構じゃないですか!盤面の重要局面以外でのカウンターと除去は、ありがたく受けておくべきです。たった1枚の《巨大化/Giant Growth》で、相手の重要な除去呪文やカウンターを誘い出せた事実に手を叩いて喜びましょう。事実、これは後半の試合結果を動かしかねない重要な出来事です。ここで使わせたカウンターや除去が、あなたのデッキに入っている重要なクリーチャー達に向けられる事は無くなったのですから。
そんな除去呪文大好きなプレイヤーには《巨森の蔦/Vines of Vastwood》をお見舞いしてやりましょう。きっとあなたの対戦相手は「テキストを確認させてください」と言ってくることでしょう。そしたらあなたは高らかにこう言ってあげてください。
「あなたの除去は対象不適正で墓地に落ち、僕のクリーチャーは強化されますッ!」ってね。
『つまり、君の対戦相手は後続の脅威の事を何も考えていないお粗末なプレイヤーだって事さ。』
1-2:《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》でブロックする場合。
あなたの場にアンタップ状態の《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》がいる状況で、タフネス1のクリーチャーでアタックしてくるプレイヤー=試合に負ける事を快感だと思えるマゾヒストなプレイヤー。(つまり弱い。)
少しマナがきつい状況でも、手札に森があったら迷わずブロックするのが懸命です。コチラは緑単色デッキ。クリーチャーに触りたくてもなかなか触れないのが現状です。向こうからわざわざアタックしてくるなら対戦相手のクリーチャーの頭数が減らせるので、1対1交換なら喜んでブロックするべきです。
「今」の盤面が辛い状況でもあなたは「クリーチャーの色」の緑。後に展開する厄介で大きなクリーチャーがブロッカーのいなくなった相手を蹂躙することでしょう。
ついでに言うなら、《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》が召喚酔いで無い状況ならば、自らをタップして先述の《巨大化/Giant Growth》を自らを対象に撃つことも可能です。カードを1対1交換した上に「場のアドバンテージ」はあなたが取れるのです。緑にとっては言う事この上無しの状況になります。
『つまり、君の対戦相手はさながら「オズの魔法使い」に出てくるカカシよりも残念なヤツって事さ。』
※また、多くのプレイヤーが「ライフ」と言うリソースを蔑ろに扱いますが、これは大きな間違いです。緑単色のデッキにとって「ライフ1点」とは、対戦相手にしろ自分自身にしろ、何物にも変えがたいものがあります。前半戦でクリーチャーをブロックに回さずに本体のライフを削られ、後半戦で並べたクリーチャーを一掃された事を考えてみて下さい。あなたが着地させたのは5/6のファッティ、相手が着地させたのは3/1のフライヤー。あなたのライフはあと3点で、相手のライフはあと6点。ほら、ライフ1点は大事でしょう?
緑単色デッキにとってクリーチャーとは「クロッカー」であり、「除去呪文」であることをゆめゆめ忘れ得ぬように。なので、場の状況をよく読み、先に繋がるプレイを見通した上で「必要最低限のブロック」をすることを心がけましょう。
======================================================
【事例2】対戦相手の動きからプレイヤーレベルを予測する
======================================================
2-1.対戦相手のフェッチランドの切り方。
対戦相手のドロー後、メインフェイズでフェッチを起動=強い。
あなたのエンドにフェッチを起動=弱い。
基本的にレガシーで使用されているフェッチランドはアンタップインが前提です。ギルドランドでも無ければ、エンドフェイズに切る意味はほとんどありません。あなたのエンドフェイズにインスタント呪文を唱えるならまだしも、あなたのエンドフェイズに何も動かないのにも関わらずフェッチを切るのは「私は先の事を考えていません」と言っているようなものです。
※ドロー後にフェッチランドを切るのであれば、たった今引いてきたカードのマナの色やコストを考慮してから持って来るカードを決められるので、ほんの少しかもしれませんが後の展開に影響する、と言うことです。つまり、細かい所まで気を配っている(隙が少ない)プレイヤーだと言うことです。
そういった「意味の無い所」で、ただ単にフェッチランドを切るようなプレイヤーは警戒心が薄い、想定外の事に弱い、基本的なマニュアル通りの戦い方しかしてこないものです。更に付け加えて言わせてもらうのであれば、あなたの呪文を全く気にしていないとまで言い切れます。
(あなたに知識がある事が前提ですが、)対戦相手の使っているカードでどんなデッキ(アーキタイプ)かが読めることと思います。そういうプレイヤーは大抵オリジナルデッキを遣っていないので、対策も立てやすいです。
そんなフェッチランドをエンドフェイズに切るのが大好きなプレイヤーには《束縛/Bind》をお見舞いしてやりましょう。きっとあなたの対戦相手は「テキストを確認させてください」と言ってくることでしょう。そしたらあなたは高らかにこう言ってあげてください。
「あなたは土地を持って来る事が出来なくなり、僕はカードを1枚ドロー出来ますッ!」ってね。
『つまり、君の対戦相手は上司にペコペコして部下に辛く当たる最低なヤツって事さ。』
※まさかその《束縛/Bind》に対して《Force of Will》を撃ってくるプレイヤーなんてまずいないでしょうが、MTGプレイヤーと言うのは本当に「損をするプレイ」が好きらしく、あながち《Force of Will》が飛んでこないとも言い切れません。
あなたが先手2ターン目で、上記の様な状況でもしも《Force of Will》が飛んできたらありがたくカウンターされるべきでしょう。「まさか土地破壊されるとは思ってなかった」という言い訳は、「緑単色相手にナメたキープするくらいなら、家に帰って彼女のケツでも舐めてろ」と言うセリフと共に、緑単色の《恐怖/Terror》を対戦相手の脳髄に刻み込んであげてください。
2-2.どのランドを持ってくるか
フェッチランドを切ってからランドを着地させるまでの時間が長い=言われるがままに高額請求サイトに会員登録をしてしまう人の良いプレイヤー。(つまり弱い。)
フェッチランドを切ってライブラリーから探している最中に「どの土地を持ってくるか」を悩んでいるプレイヤーも弱いです。
「目的があるためにフェッチを切る」のでは無く、「今、手札にあるカードを使いたいから」という理由だけでフェッチランドを切るのは先のゲームが見えていない証拠で、この上なく弱いです。また、これはフェッチランドだけに限らず、チューター系の呪文を使うときも同義です。「何が欲しいか」と言うことが明確になっていないのにカードをサーチしてくるのは愚の骨頂。だったら他の行動をした方が遥かに有効なハズです。
そういうプレイヤーは総じて「手札だけの勝負」をして来るのが常です。所謂「引きゲー」と言うモノです。「あの時○○が手札にあったら切り抜けられたのに」とか「キープ基準が間違ったかな」とか。そんな言い訳が出てくるという事は、中学生以下の脳味噌だという証明に他なりません。
マジックは基本的に60枚のデッキで構成されているのですから、どんなに頑張ろうとも基本土地カード以外は4/60、つまり1/15までしか1枚のカードを引く確率を上げられません。それが分かっているのですから、金太郎飴みたいに「何処を切っても同じような手札構成になるデッキ」か「一撃必殺の即死コンボデッキ」を使えば良いと言うことです。
そんな言い訳が出てくるようなプレイヤーは、一撃必殺のコンボデッキを使いこなせる技量も資産も無く、コピーデッキを使い、したり顔をして勝ち誇り、たまたま手札に来ていたパワーカードのカードパワーで押し切ったことを「技量」や「デッキ構築」といった言葉で覆い隠そうとするとんでもなく最低なプレイヤーだと僕は思います。
『つまり、君の対戦相手は彼女に隠れてハウツー本を読ん だ上に、彼女とのデートで優柔不断になってしまう甲斐性の無いヤツって事さ。』
【世界一の緑遣いが思うこと】
勝利と言う価値に固執して、デッキ構築や試合そのものを楽しめていない人達が非常に多いように思える昨今。「パワーカード」は過大評価され、「一クセあるカード」 は過小評価されて、淘汰されていきます。
その流れに乗っている人達は、既存のアーキタイプやカード同士のシナジーが全く取れていない所謂「ジャンク」デッキを使って(※使って=○ 遣って=×)いるんですね。僕に言わせてもらえるのであれば、現在のレガシーに存在するデッキの大多数が「ジャンクデッ キ」だと思います。
そんなデッキを使っている(否、「遣われている」)人達は、僕が頼みもしないのに 「デッキ診断」を行って来ます。このカードは弱い?色をタッチした方が強い?そんな事はお前に言われなくても、少なくともお前の1兆2000万倍は心得ている。
そういった人達は僕のデッキの何を知っているんでしょうかね?僕のデッキを回したことが無いのに、どうしてそういった「診断」が出来るのか不思議でなりません。 浅はかな知識だけで僕の崇高な「緑単色」デッキに泥を塗るのは辞めていただきたいですね。
コチラが緑含めた2マナ出せる状況で、対戦相手がコチラのエンドフェイズに手札にカウンターが無いのにも関わらず《渦まく知識/Brainstorm》を唱えるようなものなんですよ。それくらい浅はかです。《種蒔き時/Seedtime》を撃たれたらケアも出来ないクセにでしゃばるのはお門違いってものですね。
だから僕はそんな人達と試合をする気も起きないし、語り合う気も起きない。
…緑を遣うには、これくらい心を尖らせると煽りに負けないし、友達に嫌われるから戦いやすいよ!←
とまぁそんな感じです。また気分が乗ったら書こうと思います。いつになるか分からないですが。
小枝を踏み折れば、骨を折ってあがないとする。
――― ラノワールのエルフの、侵入者への処罰(心の領域的な意味で。)